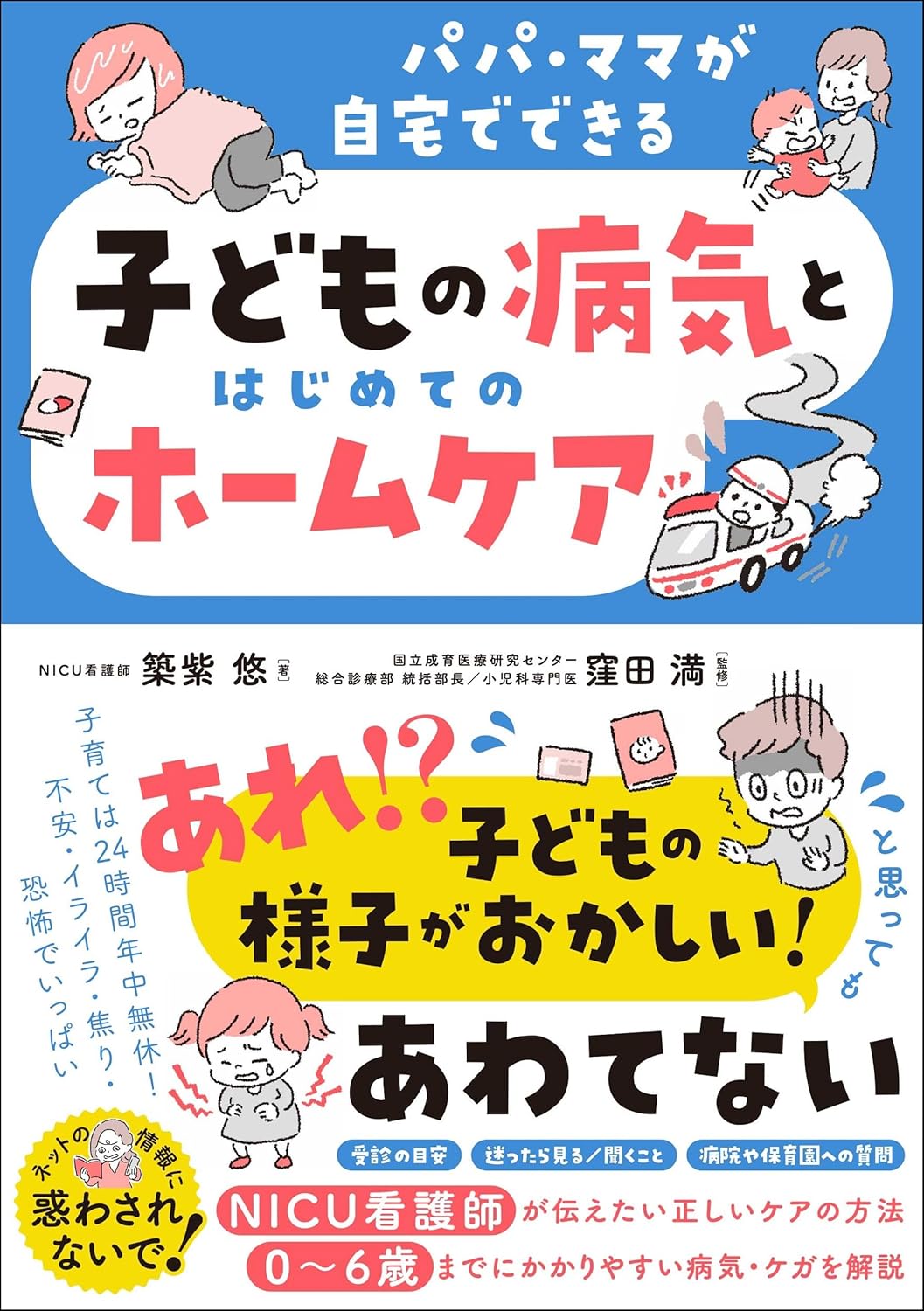「頭を打ったけど元気そう」な時は様子見で大丈夫? 子どもの転倒・転落の見逃せないサイン

公園や家の中での転倒・転落は、元気な子どもほど日常茶飯事。でも「すぐに泣いたから大丈夫」と安心していませんか?
この記事では、転倒・転落時の適切なホームケアや、受診が必要な危険サインなど、親が知っておきたいポイントを、看護師・築紫悠さんの著書より紹介します。
※本稿は、築紫悠(著),窪田満(監修)『子どもの病気とはじめてのホームケア』(総合法令出版)より一部抜粋・編集したものです。
OK:打った場所を冷やす
手足や指などを打ったり狭んだりして痛がる場合は、保冷剤をタオルでくるんで冷やしてあげましょう。冷やす目安は20 〜30 分。腫れている場合は、温めると悪化することもあるので、湯船にはつけないように。
OK:症状がなくても激しい運動を控えて様子を見る
打った直後は何事もないように見えても、体の中が傷ついていて、時間が経ってから症状が出るケースもあります。
見た目に症状はなく、いつも通り元気よく遊ぶ様子があったとしても、激しい運動は避けましょう。2 〜3日は異変がないか様子を見てください。
前日に頭を打った場合、翌朝元気がない、様子がおか
しいというときは、登園させずに病院へ行きましょう。
※頭を打った次の日に変わりなく過ごせているようであれば、登園しても問題ないと思いますが、園と情報共有をしておくとより安心です。「もし、いつもと様子が違うことがありましたら連絡をください」と伝えて。
NG:頭を打っても「泣いているから大丈夫」と軽視する
頭を打った後に、「ぎゃーっ」と大泣きすれば問題なしと考えるのは間違いです。
意識があったとしても、頭の中の小さな血管が破れ、あとから容態が悪くなることがあります。2 〜3日は安静にして様子を見ましょう。
NG:痛みのある部位を無理やり動かす
腕や脚など、打った部位がどこまで動くのか確かめるために、無理に動かそうとするのはやめましょう。ケガや骨折を悪化させてしまうリスクや、治癒を遅らせることにもつながりかねません。
NG:ケガをした部位を観察しない
軽い打ち身だと思っていても、転落や転倒で脳や内臓にダメージを受けて内出血を起こしていたり、頭や手足などを骨折していたりすることがあります。
ケガをした直後とその後の変化がとても重要です。服をまくり上げて、腫れや左右差、内出血がないか観察しましょう。
「最初はなんともなかったけれども腫れてきた」というときには受診が必要です。
緊急度
救急車をすぐに呼び、即受診する(★★★★)
・大声で名前を呼んでも目を開けない
・けいれんや嘔吐が続く
・目の焦点が定まらず、ぼーっとして、名前を呼んでもすぐに反応がない
・目のまわりや耳の後ろに赤や紫色の出血斑がある
・鼻や耳から透明の液体が出ている
・手足が変な角度に曲がっている
・顔色が青白く、腫れがひどくなる
・胸を打った後、咳き込み、苦しそうにしている
・赤い痰・おしっこが出る
・手足、指が動かない
ホームケアをしながら、日中の診療時間に受診(★★☆☆)
・体調はいつもと変わりないが、打ったところが腫れている/動かすと痛がる
・打ったあと、2〜3日様子を見ていたら赤いおしっこや黒い便が出た
・打ったり挟んだりしたあと、2〜3日様子を見ていたら腫れてきた
ホームケアをしながら、自宅で様子を見る(★☆☆☆)
・頭を軽く打ったが、その後体調に変化はなく、2〜3日経っても特別症状はない
・挟んだ後、軽く内出血はしたが、いつもどおりに動かせる
【著者紹介】
築紫悠
看護師/寄り添い疲れの人専門コーチ
北海道在住。看護専門学校卒業後、JA北海道厚生連帯広厚生病院に入職し産婦人科、新生児集中治療室(NICU)を経験。
退職後、内科、整形外科に勤務。看護師として13年、延べ2万人以上の患者と家族に寄り添ってきた。
20代でがんと診断された夫を12年間支え続けるうちに、自己犠牲による心身の消耗を痛感。自身の「寄り添い疲れ」をきっかけに、患者本人に「寄り添う言葉」が自分自身を守るものでもあるべきだと気づく。
現在は、病気の家族や介護に寄り添い続けて疲れた人に向けに、本当の自分を取り戻し、再び自分らしい人生を歩めるようフルサポートするサービスを提供中。
オンラインサロン「リトリートスペース」主宰。働きながら娘を育てる母。
窪田満(監修)
国立成育医療研究センター 総合診療部 統括部長
小児科専門医。医学博士。北海道大学医学部卒業後、埼玉県立小児医療センターなどを経て、2018年より現職。
専門は、先天代謝異常症、小児消化器病、小児総合診療(成人移行支援や小児在宅医療など)。
日本小児科学会、日本先天代謝異常学会、日本マススクリーニング学会の理事、日本小児突然死予防医学会 評議員も務める。
『パパ・ママが自宅でできる 子どもの病気とはじめてのホームケア』(築紫悠著,窪田満監修/総合法令出版)
本書は、子どもの病気やケガ・気持ちに悩まされるパパ・ママに向けて、NICU(新生児集中治療室)看護師で一児の母である著者が正しいホームケアの方法を解説します。
さらに、病院に行くか判断するために子どもの「どこ」を見るのか・「何」を聞くのか、病院や薬局で話す・聞くべき項目も掲載。
病院に行くか悩んで検索・自己判断する前に、「こんなとき、どうしたら?」と思ったら本書を見てください。