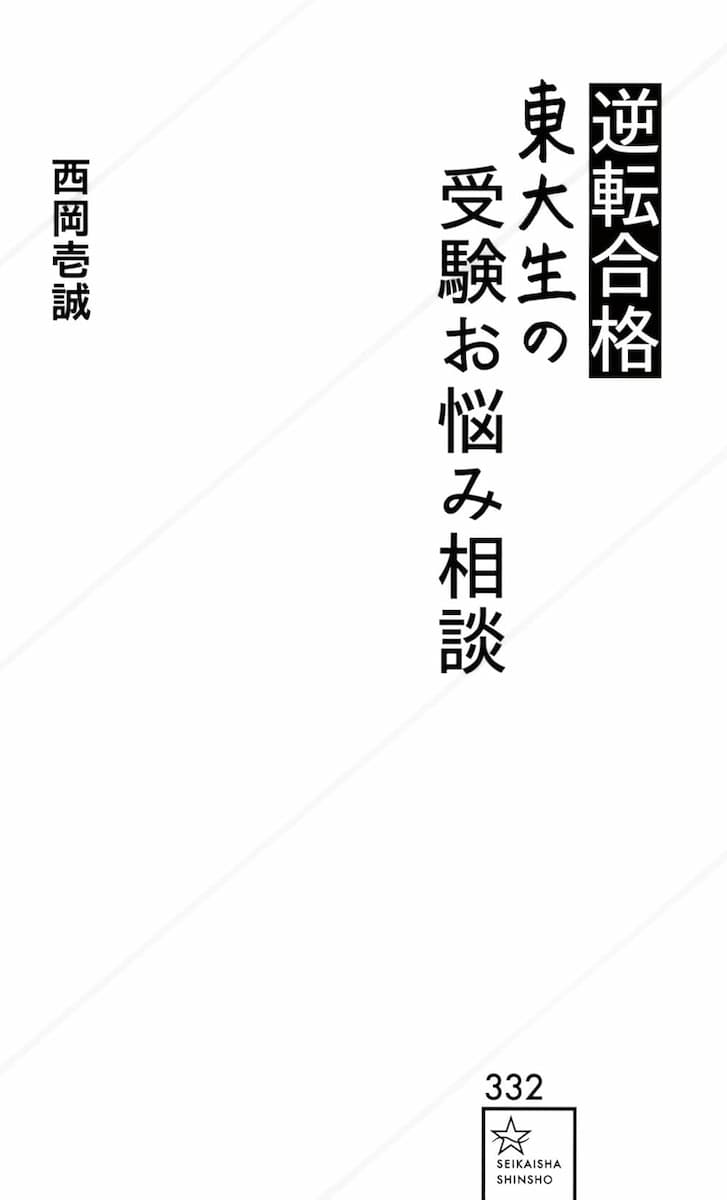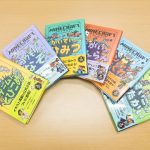理系と文系どっちを選ぶべき? 東大生作家が語る「進路選びの極意」

高校生で明確な将来の夢を描いている子どもは少ないものです。だからこそ、「志望校が決まらない」「理系と文系どっちがいいのだろう?」など、漠然とした悩みを抱えてしまいがち。
そんな悩める高校生に向けた進路選びのポイントとは? 偏差値35から2回の浪人を経て、東京大学に逆転合格した東大生作家の西岡壱誠さんの著書『逆転合格東大生の受験お悩み相談』よりご紹介します。
※本稿は、西岡壱誠著『逆転合格東大生の受験お悩み相談』(星海社新書/講談社)から一部抜粋・編集したものです。
志望校が決まらない、イメージできない

Q.目指す大学と学部が全然決まりません! 第一志望だけでなく、第二志望に関しても全然イメージできません。どんな調べ方をしたらいいでしょうか?[高校1年生 男子]
A.この悩みに関しては、「自分の学びたい教授のいる大学を探す」という方法をおすすめしています。
自分が行きたい学部の学問についての本を読んだり、自分の興味のある分野の論文を調べたりして、「この先生のもとで勉強したい」と思う教授を探してみる、ということです。
ぶっちゃけた話、「この大学に行きたい」と決めるのは難しいです。なぜなら、大学というものについて、中学生や高校生ではまだ想像が及ばないからです。それはもう仕方がないことです。だってまだ大学に行っていないんですから。「自分がどの大学に行ったら幸せになれるのか?」なんてわかるわけがないのです。
でも、「この教授の授業を受けたら楽しそうだな」というのは、具体的で想像しやすいと思います。
授業くらいであれば、きっと本や論文を読めば想像できますよね。教授や先生が話している動画なんかもネットにありますから、それを見れば「こんな先生がいるんだな」「この先生、話が面白いな」くらいのことはわかるはずです。
ということで、大学を選ぶ基準の1つとして「教授」を頭に入れておいてください。
文系と理系どちらがいいか

Q.文系に行こうか理系に行こうか迷っています! どっちの成績も平均点くらいで、やりたいこともありません。そんな状態なのに、「早く選びなさい」と先生からせっつかれています。どうすればいいですか?[高校1年生 男子]
A.文系か理系かという相談は、毎回答えに困ります。将来の職業選択や科目の好き嫌い、そういういろんな変数によって左右されてしまうものであり、「こっちがいいよ」と簡単には言えないからです。
なので、ちょっと変わり種の回答をします。ズバリ、「文系と理系、どちらが楽しく感じるのか」を探っていきましょう。
勉強が楽しい瞬間というのが、理系的な学びと文系的な学びで異なります。理系的な学びは「答えがハマる瞬間」が楽しく、文系的な学びは「答えを考える瞬間」が楽しいのです。
まずは理系から詳しく見ていきましょう。「答えがハマる瞬間」とは、パズルを楽しむような感覚です。
例えばナンプレを知っていますか? タテ9マス×ヨコ9マスの正方形のマス目があって、それが3×3の小さな正方形に分かれています。小さな正方形の9マスに、それぞれ1から9までの数字が1つずつ入るように埋めていくというゲームです。
このゲームは、「ここに3が入るんじゃないか」「こっちには8を入れれば成立するはず」とパズルを当てはめていって、全てが上手く行ったときに「楽しい」と感じられるというものです。
与えられた情報を組み立てていき、その結果として答えが1つに定まっていくのを楽しむのは、他のパズルでも言えることですね。
ジグソーパズルでも、複数のピースを組み合わせて1つの絵を作りますが、やはり楽しいのは複数のバラバラなピースが1つの絵になっていく過程と、ジグソーパズルが完成したときの満ち足りた気分でしょう。
数学にも、同じような楽しさがあります。複数の情報を組み合わせて1つの答えが出たときに、満ち足りた気分になれるというものです。
例えば東大の入試問題でこんな問題が出題されたことがあります。
「3以上9999以下の奇数aで、a² ‐aが10000で割り切れるものをすべて求めよ」
この問題、一見難しそうに見えますが、実はパズルのピースを整理して考えていくと答えが見えてきます。
そもそもa² ‐aというのは、(a‐1)×aなので、隣り合う2つの数であることがわかります。aが301だったらa‐1が300、という感じです。要はこういう「隣り合う2つの数」の積が10000で割り切れるものを求めるというだけです。
そして、10000というのは分解すると、「10000=10×10×10×10=2×2×2×2×2×5×5×5」と、2を4回と5を4回掛け合わせた数だと言えるわけです。
ここまでで止まってしまうと答えが出ないのですが、「aが奇数」という問題文の情報を使うと答えが見えてきます。
aは奇数で、その前のa‐1は偶数になりますね。aは奇数、a‐1は偶数。その答えが2を4回と5を4回掛け合わせた数。
ということは、偶数のa‐1が「2を4回掛けた数=16の倍数」で、奇数のaの方が「5を4回掛けた数=625の倍数」だとわかるのです。
625の倍数で奇数のものは、9999までで8個しかありませんから、この8個を確認していけば答えが出ます。そして答えは625だけになります。
このように、与えられた情報から1つの答えを出していく、「答えがハマる瞬間」が楽しい人は理系向きと言えるでしょう。
逆に文系の方は、答えが1つに定まらない問いに対して、様々な思考を巡らせて楽しむ傾向があります。
例を挙げれば、例えば日本は「礼儀作法」がとても重んじられる文化の国です。敬語をしっかりと使い、挨拶をすることが求められます。
いろんなマナーが存在していて、名刺の渡し方やお酒の注ぎ方・会議での座り順にタクシーやエレベーターの乗り位置など、覚えるべき礼儀作法はたくさんありますよね。
なぜ、こんなにいろんな礼儀作法があるのでしょうか?
答えを導くために、同じように礼儀作法の細かいルールがある国を思い出すと、イギリスや中国が思いつくと思います。これらの国と日本の共通点を考えれば答えが見えてくるのではないか、と考えることができます。
答えの1つとして考えられるのは立憲君主制であるということです。君主がいて、その力が強大であり、その君主に対して礼節を持って接さなければならないからこそ、敬語が生まれたりルールが生まれたりする、ということです。
具体例を挙げましょう。古文の勉強をすると、敬語の中に「天皇や皇太子に対してのみ使う最高敬語」があるのに気付きます。このように、尊敬しなくてはいけない強大な存在があると、言葉や文化としてのマナーが生まれやすいと言えるでしょう。
他にも、イギリスと日本の共通点を考えると、島国であることもマナーを育てる要因だったと言えるのかもしれません。
もちろん両国とも同一の民族で形成されているわけではありませんが、アメリカが人種のサラダボウルと言われていたり、ラテンアメリカではさまざまなルールが入り交じっていたりすることから考えると、かなり同質な人たちで作られた国だと言えます。
そうすると、人に対する「配慮」、そして「ハイコンテクストな文化」が育ちやすいと考えられるかもしれません。
日本語を覚えたての外国人があまり敬語をうまく使えなかったとしても、みんな怒ったりすることはないでしょう。
でも、日本人の後輩がタメ口で話しかけてきたら「おいおい」と言いたくなると思います。同じ文化的背景を共有する者同士の方が、人間はコミュニケーションを取るときに多くを求めると言えるのではないでしょうか。
だから、島国である日本とイギリスは、複雑な礼儀作法が求められる文化が育ったと言えるのではないでしょうか。
もちろん1つの定まった答えはありません。しかし、様々なことを考え、答えを出すために複数の物事をあれこれつなげて考えていく過程は、面白いと思いませんか?
「こういう要因も考えられるかも」「こういう背景もあるのかな」と、知識を総動員して答えを探っていく過程ならではの楽しさが、文系にはあると思います。
理系は答えがピタッと出ることが楽しく、文系は答えが1つに定まらないからこそ楽しい。そんな対比があるのではないかと思うのです。
さて、質問者さんは、どちらがより楽しいと思いましたか?
どちらが自分の気質に合っているかを考えるのも、進路を選ぶ1つのヒントになります。
西岡壱誠著『逆転合格東大生の受験お悩み相談』(星海社新書/講談社)
全国の学校や予備校で勉強法を教える著者が、学生さんや親御さん、浪人生の方への受験相談に答えた本書。偏差値35から逆転合格した経験をもとに、勉強の意義から勉強習慣の作り方、保護者の受験への関わり方まで、幅広い悩みを解決します。
大学入試のシステムも変わり、通信制高校によるオンライン教育の変化なども見られる現代。悩み多き受験生や受験生の親へのヒントがつまった一冊です。