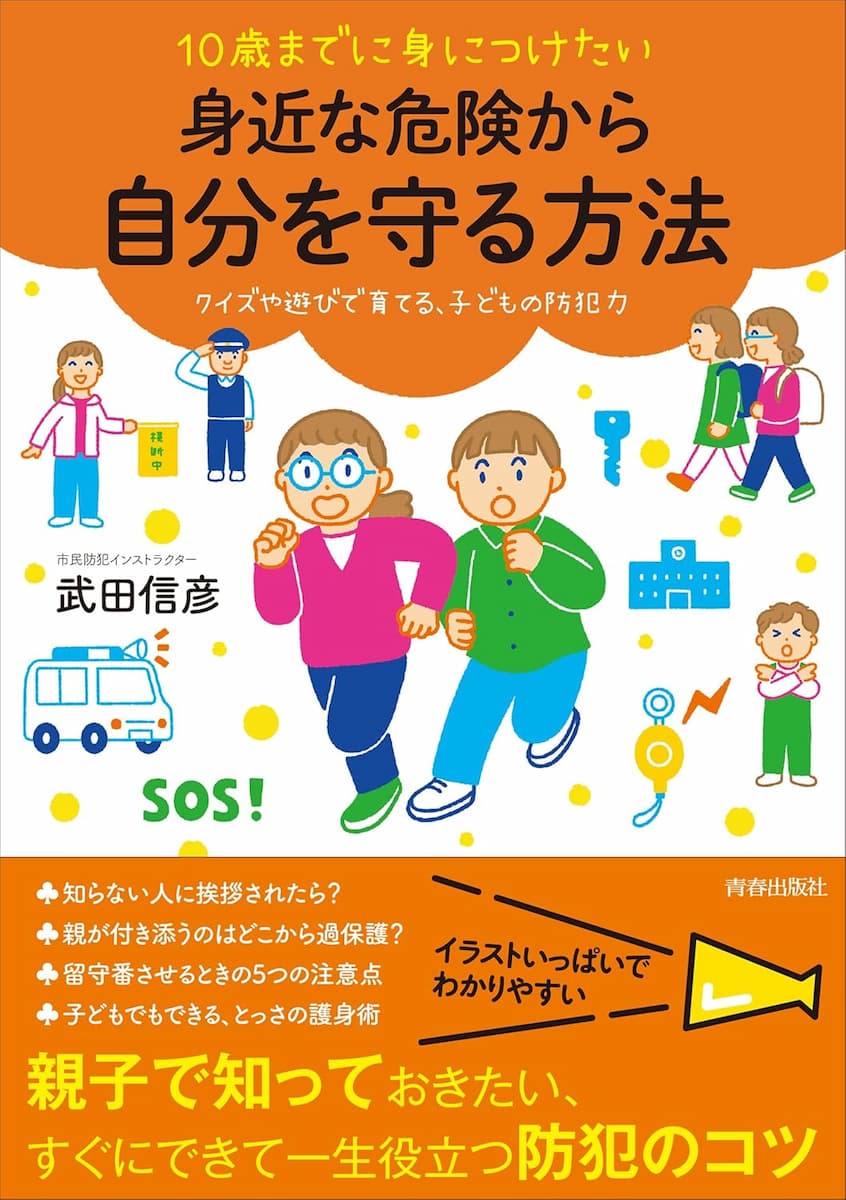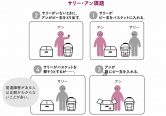子どもの登下校が不安…付き添いNGでもできる「防犯対策」とは?

子どもの登下校に大人が付き添うことは、大きな防犯力につながります。
しかし実際には、仕事などの事情で付き添いが難しい家庭も多いのではないでしょうか。
では、子どもに付き添えない場合、どんな防犯対策ができるのでしょうか?
防犯の専門家・武田信彦さんの著書から、今日からできる対策をご紹介します。
※本稿は武田信彦著『身近な危険から自分を守る方法』(青春出版社)より一部抜粋・編集したものです。
Q 働いているから子どもに付き添えないのだけど…
A「玄関先からの見送り」も効果アリ 実行できる防犯対策を見つけよう
いま、日本では、子どもだけになりやすい環境が広がっています。その背景としては、①文化・習慣的に子どもだけになりやすい(地域育ての文化・習慣)、②家族構成や働き方の多様化により、大人と子どもの時間が合いにくくなった(社会環境の変化)などが挙げられます。
学童保育(放課後児童クラブ)の利用人数も年々増加。 こども家庭庁によると、2024年時点で、約152万人となり過去最多を更新したとか。その反面、「学童クラブに登録できない」「学童クラブに馴染めない」などの理由から、自宅で留守番をしている子どもたちもおおぜいいます。
今後、登録数の増加は落ち着きそうですが、利用人数の高止まりは続くでしょう。最近は、早朝に出勤する保護者も多く、学校が開くまで、校庭などでの「朝の見守り」の必要性も高まっています。
子どもの防犯対策では、海外との比較を交え、保護者の“自己責任”を問う声も聞かれます。しかし、犯罪被害が懸念される「子どもだけになりやすい環境」は、地域の成り立ち、文化習慣、人々の暮らしや環境の変化等が絡み合って生じています。
つまり、防犯対策を子どもや保護者にだけ押し付けることは不可能。地域社会全体で取り組むべきです。政府や関係機関でも、見守り・助け合いがベースの子どもの防犯対策を推進しています。
とはいえ、身近な大人の付き添いこそが最強の防犯対策ですから、可能な範囲での見守り・付き添いをおすすめします。
玄関先に出て姿が見えなくなるまで見送る、集団登校の待ち合わせ場所まで付き添う、
防犯ボランティアの方たちがいる交差点まで付き添う、または、近くの交差点へ迎えに行く、放課後児童クラブへの送迎など、日々の生活の中で実行できる防犯対策を見つけましょう。
「付き添いは過保護?」とは思う必要はありません。なによりも、子どもの安全を一番に考えてください。
武田信彦著『身近な危険から自分を守る方法』(青春出版社)
学校・塾・習い事・スポーツ活動など、親の手から離れる時間が増えてくると、子どもがひとりで行動する場面も広がっていきます。 家族と一緒に出掛けた場所でも、家の中でも、じつは「ひとり」のシーンは案外多いもの。
だからこそ、子ども自らが「自分の身を守る」力を育ててあげましょう。クイズやゲーム感覚でできる防犯力の高め方を中央省庁をはじめ、自治体や教育委員会、警察等からの信任も厚い子どもの防犯のスペシャリスト・武田信彦先生が徹底解説。
家庭はもちろん、教育関係者や自治体まで、子どもの防犯に取り組む方々には必携の一冊です。