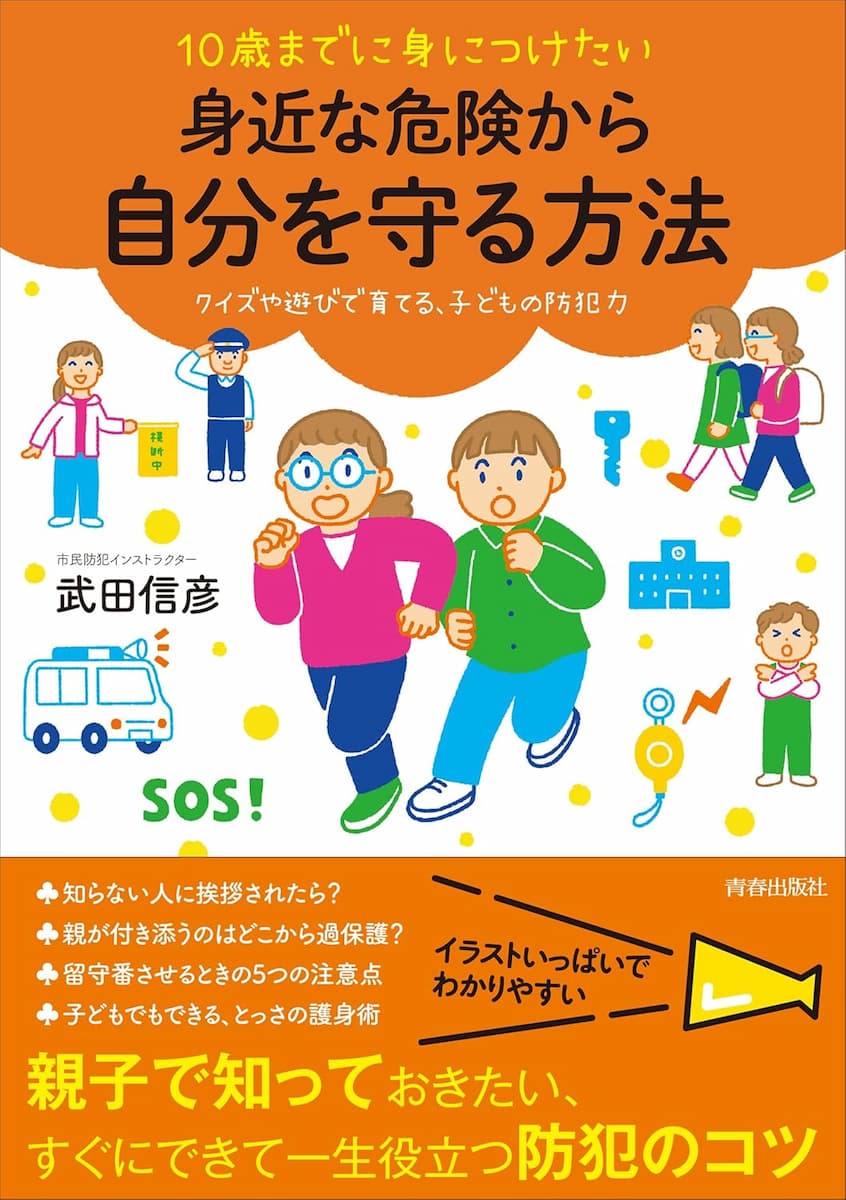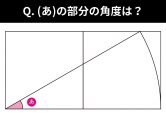「不審者・知らない人」では見抜けない 子どもに教えたい“危険な人物“の見分け方

子どもに防犯を教えるとき、「知らないおじさんに気をつけてね」と声をかけていませんか?
でもその言葉、じつは子どもの警戒心を鈍らせてしまう可能性があるのです。
防犯の専門家・武田信彦さんが語る、本当に注意すべき「危険な人」とは?
著書から抜粋してご紹介します。
※本稿は武田信彦著『身近な危険から自分を守る方法』(青春出版社)より一部抜粋・編集したものです。
Q 危険な人ってどんな人ですか?
A 悪意・犯意をもつ人は外見ではなく行動で判断すべき!
「子どもへ声をかけた“不審者“は、短髪、メガネ、中肉中背、黒っぽい服を着た40代前後の男」。自治体の会合で、共有された不審者情報は、その日の私の風貌と一致していました……。
犯罪への警戒心が高まると、悪意・犯意をもつ「人」へ厳しい目が向けられます。そして、“不審者“という警戒すべき人物像を生み、無関係な人にまでまらぬ疑惑の目が。安全を理由に、社会に差別や排斥が発生する第一歩といえます。
子どもや地域の安全は、守らなければいけない。一方、過剰な防犯により、不快な思いや生きづらさを覚える人が生まれてはいけない。防犯には、このバランス感覚が必要です。
また、「特定の人物像を絞った防犯啓発」では、防犯対策自体が弱まる危険性があります。
いまだに耳にする「知らないおじさんに注意」の防犯指導。その結果、「知っている人」「おじさん以外のキャラクター」への警戒心が緩みます。しかし、子どもへ悪意や犯意を向ける者には、元家族や知人など「知っている人」もいるのです。
また、年齢は関係ないうえ、女性による犯罪も。「刃物を持っている」など、明らかに危険とわかるケースを除き、見た目だけで悪意や犯罪を判断するのは、ほぼ不可能です。
結局のところ、その人の“言動“が警戒の見極めになります。たとえば、近づいてくる、ついてくる、撮影しようとするなど、「あれ、変だな?」と感じる行動。また、誘ってくる、お願い事をしてくる、プライベートな情報を聞き出そうとする等、違和感を覚える声かけにも警戒しましょう。
ところで、いわゆる「不審者メール」には、「“こんにちは“と声をかけられた」「“がんばれよ!“と言われた」など、健全にも思える事例もあります。「過剰反応では?」「やりすぎ!」と思われがちですが、発言時の態度や言い方を含め、警察や関係機関が危険性を判断していますから、一概に「やりすぎ」と言えないのです。
武田信彦著『身近な危険から自分を守る方法』(青春出版社)
学校・塾・習い事・スポーツ活動など、親の手から離れる時間が増えてくると、子どもがひとりで行動する場面も広がっていきます。 家族と一緒に出掛けた場所でも、家の中でも、じつは「ひとり」のシーンは案外多いもの。
だからこそ、子ども自らが「自分の身を守る」力を育ててあげましょう。クイズやゲーム感覚でできる防犯力の高め方を中央省庁をはじめ、自治体や教育委員会、警察等からの信任も厚い子どもの防犯のスペシャリスト・武田信彦先生が徹底解説。
家庭はもちろん、教育関係者や自治体まで、子どもの防犯に取り組む方々には必携の一冊です。