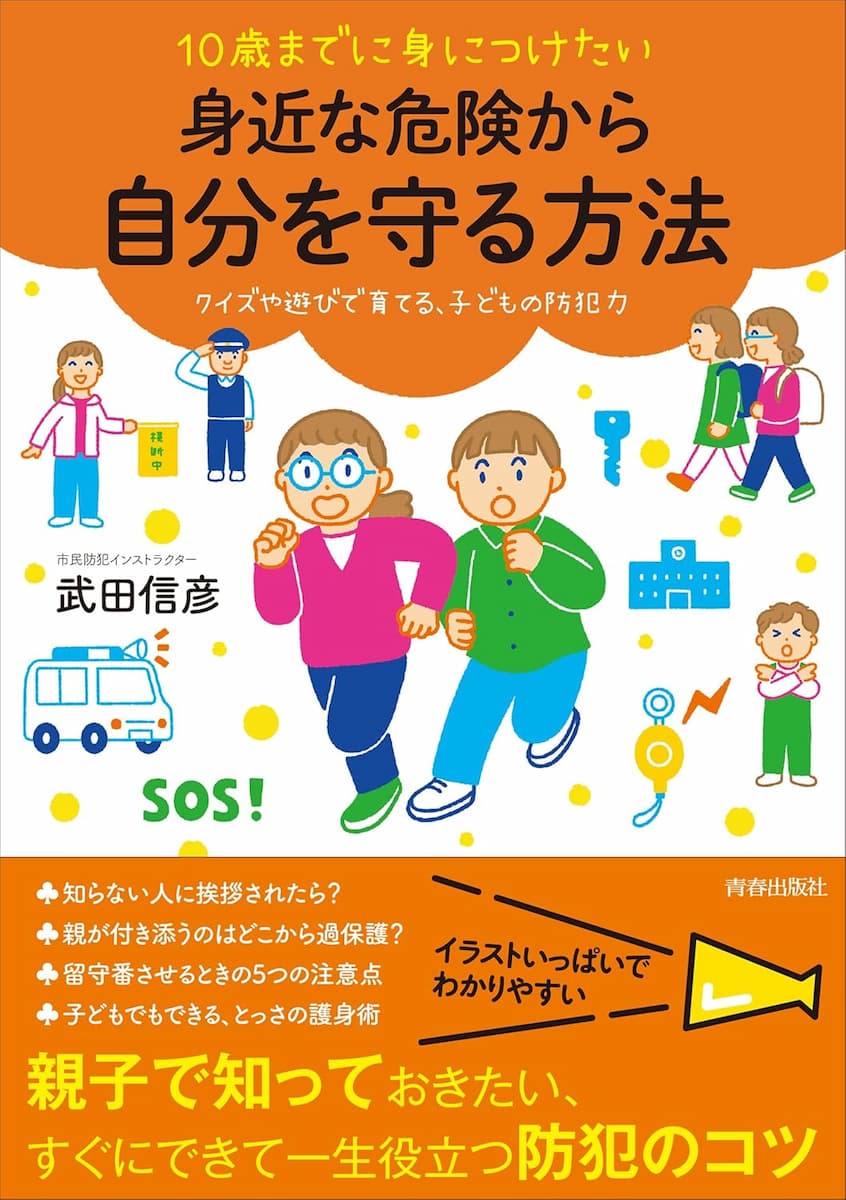「知らない人とは話さない」の落とし穴とは? 専門家が語る本当の防犯力
子どもに近所の人とあいさつをさせるべきか、それとも「知らない人とは話さない」のルールを徹底させるべきか……今の時代、こんな葛藤も珍しくないかもしれません。
しかし、防犯の専門家・武田信彦さんによると、あいさつは子どもの防犯につながる力になるのだそう。
あいさつの役割と正しい付き合い方を、著書より抜粋してご紹介します。
※本稿は武田信彦著『身近な危険から自分を守る方法』(青春出版社)より一部抜粋・編集したものです。
Q あいさつなんてしなくてもよいのでは
A あいさつは防犯の基礎力! 距離感を保ちあいさつしよう
「子どもたちへ挨拶をしたら『知らない人とは話さない!』と言われた」「見守り活動中、子どもたちへ声をかけにくい」。各地の防犯ボランティア研修会で、こんな声が聞こえてきます。
世代を超えて健全なコミュニケーションが育まれている地域も多い一方で、子どもたちへの「あいさつ」や「声かけ」がしにくいと感じるケースも増加。子供を狙う犯罪への不安から、過剰な防犯意識が生まれ、「悪意や犯意を持つ者と遭遇しないよう、あいさつも止めたほうがよいのでは?」といった風潮が垣間見えます。
あいさつは、子どもの防犯対策には欠かせない“基礎力“です。あいさつは、人を無視しません。お互いに小さな“信頼“が芽生え、見守り・助け合いの力が強くなります。万が一の際の、「助けて!」を伝える練習でもあります。
また、あいさつがなくなれば、見守りや防犯活動は弱体化。人から無視される環境で、地域活動を持続させるのは困難だからです。結果、「子どもだけになる瞬間」はますます増え、悪意や犯意をもつ者が犯罪を実行しやすい環境が増える危険性も。
つまり、過剰な警戒心は、多くの善意を退け、悪意・犯意に負ける結果を招くのです。
いま、求められるのは、「あいさつと防犯の両立」です。あいさつは、誰とかわしても問題ありません。ただし“触られない距離感“を保つこと。お互いの安全を守りあうマナーでもあり、「あいさつと防犯の両立」を実践するコツです。
さらに、体の距離感と同時に、心の距離感も大切。身を守るためには、悪意や犯意をもつ者に心身をコントロールされぬよう、誘い、お願いごとなど、違和感を覚える声かけには、「できません!」ときっぱり断り、すぐに逃げる!
あいさつをするorしないは、個人の自由ですが、防犯対策としては「しなくてよい」とは言えません。なぜなら、子どもたちがピンチの際に「助けて!」が言えなくなる危険性もはらんでいるから。あいさつなど、地域のコミュニケーションを大切にし、人と人との接し方・距離感を学びながら、防犯力を強めたいものですね。
武田信彦著『身近な危険から自分を守る方法』(青春出版社)
学校・塾・習い事・スポーツ活動など、親の手から離れる時間が増えてくると、子どもがひとりで行動する場面も広がっていきます。 家族と一緒に出掛けた場所でも、家の中でも、じつは「ひとり」のシーンは案外多いもの。
だからこそ、子ども自らが「自分の身を守る」力を育ててあげましょう。クイズやゲーム感覚でできる防犯力の高め方を中央省庁をはじめ、自治体や教育委員会、警察等からの信任も厚い子どもの防犯のスペシャリスト・武田信彦先生が徹底解説。
家庭はもちろん、教育関係者や自治体まで、子どもの防犯に取り組む方々には必携の一冊です。