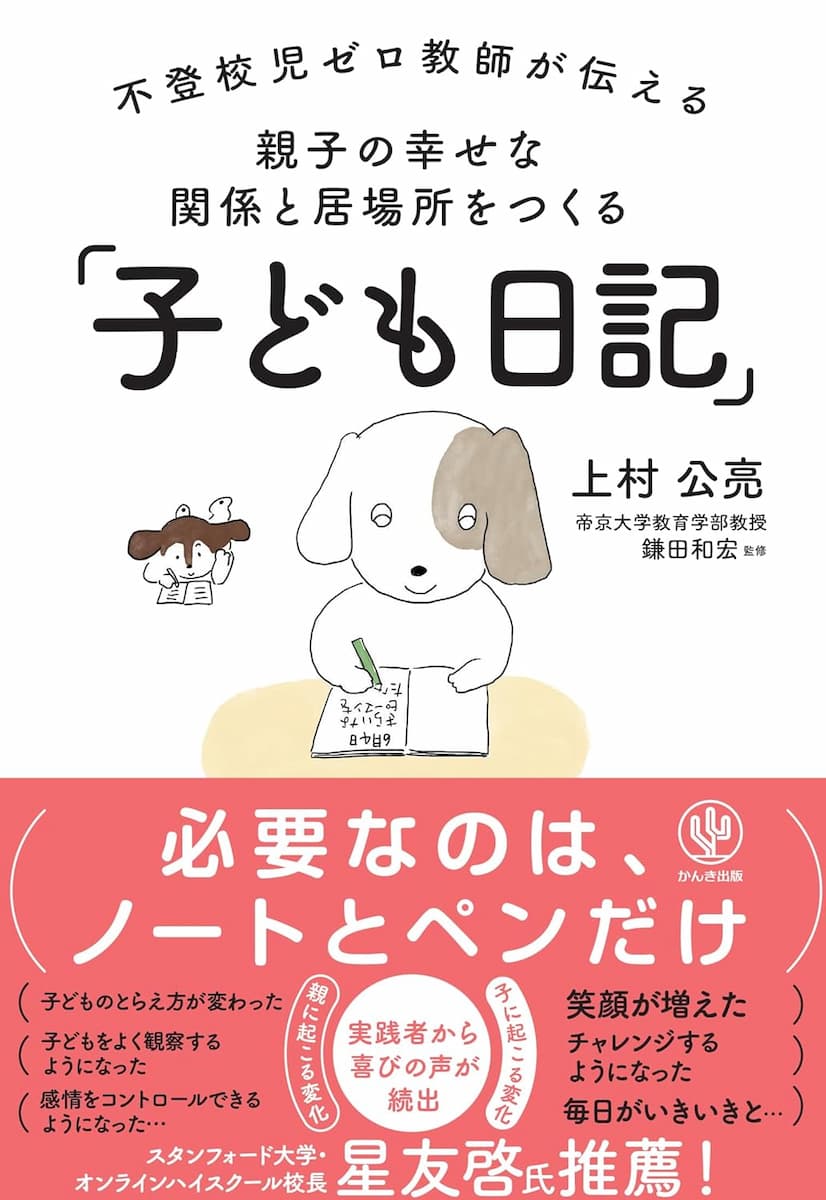子どものコンディションは“字“に現れる 親子コミュニケーションに「交換日記」がおすすめの理由
子どもが大きくなるにつれて、「なんだかコミュニケーションがうまくとれないなあ」と悩むことはありませんか? 元小学校教師で、特定非営利活動法人この子キャリア応援団団長の上村公亮さんは、親子で交換日記をすることを勧めています。その名も「ラリー日記」。
LINEのやりとりだけでは生まれにくい、手書きノートならではの効果について、上村公亮さんの著書『不登校児ゼロ教師が伝える 親子の幸せな関係と居場所をつくる「子ども日記」』からご紹介します。
※本稿は上村公亮(著)鎌田和宏(監修)『不登校児ゼロ教師が伝える 親子の幸せな関係と居場所をつくる「子ども日記」』(かんき出版)から一部抜粋・編集したものです。
令和時代の手書きコミュニケーションツール「ラリー日記」
子どもとのコミュニケーションをもっととりたいと思ったときにおススメしているのが「ラリー日記」です。
これは子どもとの交換日記です。お子さんの書いた文章に親御さんが感想を述べたり、親御さんが気になっていることを吐き出して、お子さんに読んでもらったりすることで、お互いの理解が深まっていきます。
「ラリー日記」はノートとペンがあれば、今日からでもできます。
ノートは罫線があるタイプでも、罫線なしの無地のタイプでも、使いやすいノートでかまいません。ただ、すぐに1冊がいっぱいになってしまうので、あまり高価な日記帳より、数百円のノートのほうがいいと思います。
パソコンやスマホで打ち込むより、手書きを断然おススメします。文字がうまいも下手も関係ありません。
「ノートに書かなくても、LINEでやりとりすればいいのでは?」というご意見もあるでしょうが、手書きだからこその意味があります。
まず、字にはその時々の感情や体の状態が現れます。
怒っているときには字が乱れていたり、疲れているときは雑な字になっていたりして、自分や子どもがその日どのような状況だったのかがわかります。薄い字や濃い字、急いで書いた字、嬉しいことがあったときの弾むような字など、字からも多くの情報をもらえます。
また、肉筆からは温かさを感じます。
皆さんも、印刷された年賀状をもらうのと、手書きの年賀状をもらうのとでは、喜びの度合いがまったく違うでしょう。その人の字は世界に一つしかない字なのです。
「いいね!」「よくできました」という一言でも、文字に書くのと、スタンプで済ませるのとでは印象がまったく違います。スタンプだと誰が送っても同じなので、あまり心は動きません。
それに、スマホだと長文を読むのも打ち込むのもつらいので、短文になりがちです。
「今日は宿題を忘れて先生に叱られた」「今度から気を付けてね」という短いやりとりを繰り返すだけだと、お互いの距離感はそれほど縮まらないでしょう。
そのうえ、スマホやパソコンだと文字の予測変換機能があるので、すべてを打ち込まなくても文章をつくれます。それだと個性が出にくい気がします。
「どう伝えればいいのか」と頭をひねりながら、自分の字で書くから、唯一無二の気持ちが込められると思うのです。
やはり、手書きが少なくなってきた今だからこそ、手書きは貴重なのだと思います。
ただ、手書きが苦手な子もいます。タイピングや音声入力、シールを貼るなど、その子が表現しやすい方法で続けることが大切です。
また、子どもから返事がなくても書き続けている親御さんや、書いた文章をお子さんに読み上げている方など、工夫されている親御さんもいらっしゃいます。
「親の関心」を子どもに届けられ、コミュニケーションのトレーニングができる
皆さんは、子どもたちが一番欲しいものは何だと思いますか?
クリスマスのシーズンにおねだりするオモチャやゲーム、スマホではありません。私が今まで大勢の子どもと関わってきた経験から言えるのは、「他者からの関心」です。
親に関心を持ってほしいと、親が考えている以上に、子どもたちは切実に望んでいます。親だけではなく、先生などの大人や、友達にも認められたいと思っています。
その気持ちがさまざまな形で表れて、友達にちょっかいを出して泣かせてしまったり、親が「やめなさい」と注意すればするほど、暴れたりするのだと考えられます。子どもは自分の感情をうまく言葉で表現できないから、まったく違う行動で表してしまうのですね。
「ラリー日記」は、まさに親が子供に関心を持つためのツールです。
もちろん、皆さんもお子さんに対して関心を持っているから、日々悩みながら衝突しているのだと思います。
でも、その思いがお子さんにきちんと届いていない場合があります。
お子さんの心に届いていないのはなぜなのか。
お子さんの話を最後まで聞こうとせず、途中で遮っているからかもしれません。親御さんが何気なく言った言葉に傷ついているからかもしれません。
あるいは、お子さんがSOSを出しているのに、気づいてあげられない場合もあるでしょう。
親になるトレーニングを受けて親になる人はいません。
2人目、3人目の子どもなら、ある程度は経験則で対処できるでしょうが、それでもそれぞれの子どもの性格は違うので、予測不能なことばかり起きるでしょう。
野球ではいきなり投げられたボールを打つのは簡単ではありませんが、止まっているボールなら打ちやすくなります。
止まっている蝶はつかまえられますが、飛んでいる蝶をつかまえるのは至難の業です。
コミュニケーションも相手がどのような発言をするのかわからないのに、その場のアドリブで受け答えしようとするから、お互いに思いを伝えられずにヒートアップしてしまって、収拾がつかなくなるのかもしれません。
ラリー日記は「止まっているコミュニケーション」のトレーニングになります。
お子さんの書いたコメントに対して、「どうやって返せばいいのか」と考えてから自分の思いを書くというラリーを繰り返すうちに、「こういう場面ではこう返せばいいんだ」とコツがつかめてきます。
心の中の感情を暴走させないように、理性の手綱でコントロールするのです。
止まっている段階でしっかりと返せるようになったら、普段のコミュニケーションでも落ち着いて対処できるようになっていくでしょう。
「ラリー」ではなく一方通行でもいい
「ラリー日記」を始めるにあたって、小さいお子さんは「やってみる?」と聞いたら、たいてい「やってみる」と話に乗ってくれますが、大きくなるにつれ、抵抗感が芽生えるようです。
お子さんが中学1年生で始めたご家庭は、なかなか返信をもらえないと話していらっしゃいました。
そのご家庭は息子さんが思春期に突入して、お父さんと全然口をきいていない状況だったので、「それなら『ラリー日記』をしてみては?」と勧めました。息子さんが「やる」と言わなくても、お父さんが勝手に始めて、日記を書いています。
「ラリー日記」は「バレてもいい日記」というより、むしろ「バレたほうがいい日記」です。そこで、日記を家族で食事をするテーブルの上にさりげなく置いておいたり、玄関に置いておくなど、いろいろと作戦を練って試していらっしゃいます。
こういう場合、お子さんにムリヤリ書かせても意味はないので、本人が書く気になるまで待つしかありません。返信はなくても、「お父さんはこんなことを考えてるんだな」と本人に伝わるだけでも大きな意味があると考えています。
一方通行だと親御さんがめげてしまいそうですが、まずはお子さんが毎日読めるチャンスをつくってあげてほしいと思います。返信を書かずに反抗しているのも一つの甘えなので、そのお子さんの状態を丸ごと受けとめることもまた、愛情表現だと言えます。
上村公亮(著)『不登校児ゼロ教師が伝える 親子の幸せな関係と居場所をつくる「子ども日記」』(かんき出版)
必要なのは、ノートとペンだけ
スタンフォード大学・オンラインハイスクール校長 星 友啓氏推薦!
実践者から喜びの声が続出
親に起こる変化
・子どものとらえ方が変わった
・子どもをよく観察するようになった
・感情をコントロールできるようになった…
子どもに起こる変化
・笑顔が増えた
・チャレンジするようになった
・毎日がいきいきと…