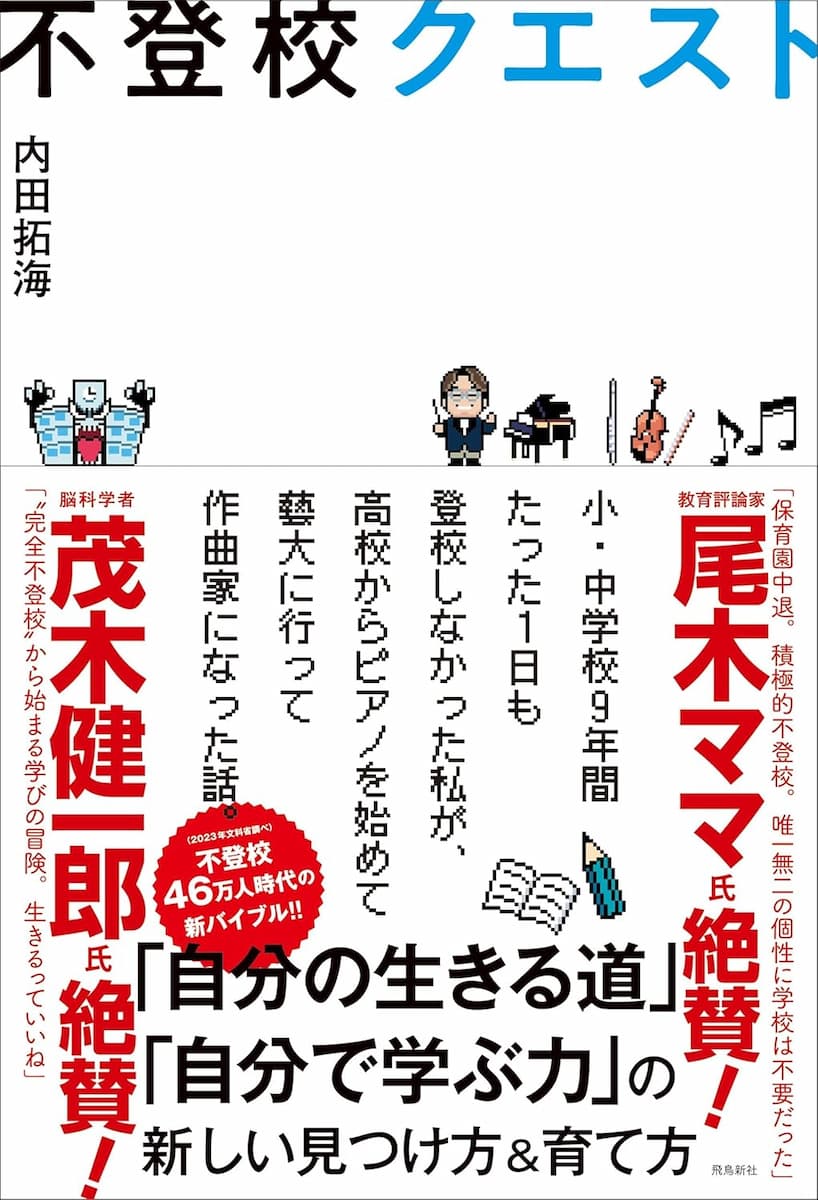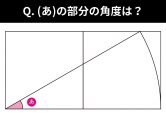学校行かず何してた? “9年不登校“を貫いた作曲家が振り返る「毎日が夏休み」の少年時代

小・中学校の9年間、一日も学校に通わなかったという、作曲家の内田拓海さん。
「毎日が夏休み」だったという日々の中で、内田さんはどのような少年時代を過ごしたのでしょうか。
ご自身の著書『不登校クエスト』から、一部を抜粋してご紹介します。
※本稿は内田拓海『不登校クエスト』(飛鳥新社)より一部抜粋、編集したものです。
“ゲーム” “公園” “お絵描き”三昧の「毎日が夏休み」

「小学校に行かないで、毎日何をしていたの?」
そんな質問をよくいただきます。普通に通学していた人からすると、不登校の子どもの一日はイメージがしづらいかもしれません。
学校に行かない生活というのは、朝起きてから夜寝るまですべてが“自分の自由時間“です。言ってみれば「毎日が夏休み」。私は教材やドリルを使うような普通の勉強はほとんどしませんでした。ひたすら遊んで、不思議に思っていることについて、好きなだけ考え続けていられる、エキサイティングな日々でした。ひとりで、思い通りに気ままにできることがたくさんあって、とにかく面白かった。
朝8時、9時くらいに起きたら朝ごはんを食べて、まずゲームをします。午前中のゲームは少しだけにして、その後は外に遊びに行きます。遊び場はいくらでもありました。近所の公園や駄菓子屋はほとんど毎日行く場所でした。
近所の同世代の子どもたちはみんな学校に行っているので、基本はいつもひとりです。自転車に乗って公園に行って、ぐるぐる歩き回ってみたり、キレイな形の石を拾いに行ったり。公園の帰りに駄菓子屋に寄ると、買い物に来ている近所の人に「あれ? 学校はどうしたの?」なんて、心配されたり、驚かれることもありました。
近くのイトーヨーカドーも私にとっては重要な遊び場のひとつ。イトーヨーカドーのおもちゃ売り場には、色々な形や色のおもちゃがあるので子どもにとっては美術館のようなものでした。その年齢くらいの子どもは、何をしていても楽しいのです。
寂しいと思ったことは一度もない

外から帰ってきて、昼ごはんを済ませたら、本格的にゲームの時間が始まります。
子どもの頃の私はとにかくゲームが何より好きで、時間さえあればとにかく延々とやっていました。そのほとんどがRPG。『ファイナルファンタジーⅥ』や『クロノ・トリガー』といった超名作を毎日何時間も、時には晩ごはんも食べずに夢中になっていました。それでも両親は、「ゲームばっかりしてないで!」と、私を咎めたことはほとんどありません。
徹底して、「やりたいように生きる」ことを認めてくれました。
そうそう。ゲームというと、世代的にはちょうど『遊☆戯☆王』や『ポケットモンスター』といったトレーディングカードゲームが流行していました。ゲーム好きの私としては、ちょっと興味はあったのですが、何せいつもひとりなので“対戦相手“がいません。ですから私にとっての楽しみ方は、カードを買って、並べて眺めること。
よくよく見てみると、同じキャラクターでも色々な絵柄があったり、レアなカードにはホログラム加工がされていたりして、見ているだけでも面白かったのです。
ちょっと寂しそうにも思えるかもしれませんが、私としては何をしていても「楽しい」という気持ちが上回っていて、寂しいと感じたことはありませんでした。ゲーム以外では、絵を描くことも日課のひとつ。
私は小さい時から絵を描くことが好きで、やはり寝食を忘れるほど、夢中になる時もよくありました。好きな漫画のキャラクターを描いたり、幾何学的な模様だけをひたすら描いてみたり、父が趣味でやっていたボディボードに絵を描かせてもらったり、自分で空想した奇妙な魚の絵を描いて、架空の図鑑を作ったりもしました。一日中こんな調子です。
やりたいことがたくさんあり過ぎて、毎日が日曜日でも足りないくらいでした。
自分のやりたいように「好きなことを学ぶ」

基本的に毎日「起きて、遊んで、寝る」の繰り返しでしたが、私自身が勉強や学習が嫌いというわけではありませんでした。
むしろ学ぶことは好きでした。ただしそれが、自分の興味のあるものだけ、やりたいものだけ、ではあるのですが。
本もやはり自分の興味があるものを好きなだけ眺めたり、何度も読み返しました。特に印象深いのは小学館が刊行していた図鑑シリーズ。家に何冊か買ってもらったものが置いてあり、中でも『昆虫の図鑑』が私のお気に入りでした。どちらかと言うと、虫は苦手なほうなのですが、図鑑を通して見ると、その不思議な模様や生態の解説にに夢中にさせられ、何度開いても飽きることはありませんでした。
多くの子どもたちの憧れでもあった、学研の学習雑誌『〇年の科学』も、私のお気に入りでした。読み物や連載マンガだけでなく、自分で〝名前シール〟を作ることができるラベルプリンターや草をすり潰して観察する謎の器具、生物飼育セット……等々、毎号楽し気な付録がついてきて、ちょっとした実験ができることが面白かったのです。また、自分の学年にこだわらずに好きな号だけを購読をしていた、ということもその面白さに輪をかけていました。
例えば、私が9歳の時でも3年生向けのものではなく、本来は6年生向けの『6年の科学』を読んだりしていたのです。
「うーんと……1月号は『4年の科学』、2月号は『6年の科学』、3月号は……これは『3年の科学』にしよう」
年間刊行スケジュールには、各学年と各月ごとに予定している特集や付録が予告されています。その予告を見て、自分が「面白そうだな」と思ったものを虫食い式にひとつずつ選んで買ってもらっていました。
「2年生だからコレね」と決められたものを買うのが嫌だったというよりも、単純に「気になるものを読んだほうが面白い」
と思っていたからです。ただし、各学年ごとに掲載される連載マンガが“歯抜け“になってしまってきちんと読めないことだけは、この方式の唯一の欠点でしたが。
習い事も自分のやりたいこと、興味があることだけ。
10歳くらいの頃から、絵画教室と英語教室に通い始めました。英語は、ふと「ちょっとやってみたいな」と思って、私から両親に「習わせて欲しい」とお願いして始めました。こちらは教室の雰囲気がそれほど合わなかったこともあり、あまり長くは続かなかったのですが、絵画教室は母が「行ってみる?」と提案してくれました。私がたくさん描いている様子を見ていて、「好きなことを伸ばしてあげよう」と考えたのかもしれません。
近所にあったその絵画教室は、水彩でも油彩でも自由に描かせてくれるところで、ほかの子どもたちと一緒に絵に集中できました。
ただ一度、その絵画教室で行くことになった“サマーキャンプ“だけは「嫌だな」と感じたことを覚えています。キャンプに参加してみると、ほとんどの子どもは良くも悪くも“普通“の子どもで、落ち着きなくはしゃぎ続けるその子たちと一緒に寝泊まりすることはストレスでした。もちろん、傍から見れば私もそのはしゃいでいた1人だったと思いますし、すべてが悪い思い出ではないのですが……。
ここまで読んで、読者の中にはお気づきの方もいると思います。この時点で、私は音楽教室にも通っていませんし、ピアノを習ったりもしていません。
当時の私にとっては、音楽よりも英会話、絵のほうが興味があることだったのです。
そんな私が10年後には藝大の音楽学部に入り、作曲家になるのですから、人生はわかりません。
内田拓海『不登校クエスト』(飛鳥新社)
教育&学びの第一人者、大絶賛!!
「保育園中退。積極的不登校。唯一無二の個性に学校は不要だった」
――教育評論家・尾木ママ
「“完全不登校“から始まる学びの冒険。生きるっていいね」
――脳科学者・茂木健一郎
小・中学校9年間、たったの1日も通学せず、高校からピアノを始めて藝大に入った26歳作曲家が考える「自分で学ぶ力」「自分の生きる道」の新しい見つけ方&育て方!!
6歳で自ら「学校に行かない!」と宣言し、ホームスクーラーとなった作曲家…内田拓海さんによる自伝的エッセイ。生きづらさに苦しむ子ども自身はもちろん、子どもの教育、学校との向き合い方に悩む親の背中を押してくれる「人生を切り拓くヒント」満載の一冊。不登校46万人時代の新バイブルです。