HSCの子どもが安心して一歩を踏み出すために 専門家が教える“心を守る習慣

「初めてのことに強い不安を感じ、なかなか行動に移せない」というHSC(繊細な子)の困りごとあるある。環境の変化にゆっくり順応するHSCのために、親ができるサポートとは?
HSCの母親としての経験を生かし『発達科学コミュニケーション』マスタートレーナーとなった、むらかみりりかさん。繊細な子どもが安心して新しい世界への一歩を踏み出すコツを紹介します。
※本稿は、『HSC・繊細な子の育て方がわかる!ペアレントトレーニング』(むらかみりりか/パステル出版)から一部抜粋・編集したものです。
環境に慣れるまで人の何倍も時間がかかります
初めてのことに全力拒否をしがちな繊細な子は、行動する範囲や量が限定的になり、脳も経験不足になります。脳は経験したことを学習・記憶して伸びますから、経験が足りないと環境に慣れるのに時間がかかってしまうのは当然です。
私の息子は、3学期になってやっと「今日、お友だちが1人できた」と言うような子でした。「えっ? 3学期になって、今頃?」と私は心配になりましたが、それくらい繊細な子は環境に慣れるまでに他の子の何倍も、何十倍も時間がかかるのです。
解決エピソード
繊細な子が初めての環境にスムーズに慣れるためには「予習」がおすすめです。例えば、進級・進学にあたり、年度初めはクラス替えや担任の変更がありますよね。
新年度の初日に新しい教室に入り、新しい担任の先生、新しい友だちを目の前にすると、
繊細な子は過度な緊張と不安に襲われるでしょう。
それを少しでも緩和してあげるために、あらかじめ学校に相談して、春休み中にひと足早く新しい担任の先生に会わせてもらったり、新しい教室に入らせてもらったりと、「予習」をしておくのです。
「この先生、知ってる」「ここ、来たことがある」と見通しが立つことで「だから大丈夫!」と安心でき、新しい環境に適応しやすくなります。
「友だちをつくる」ことにも「予習」は有効です。「同級生はみんな友だち」と思う子どもがいる一方で、わが家の繊細くんは「クラスメートに『友だちになろう』と聞いて『いいよ』と言われたら友だち」だと言っていました。
彼が友だちにそう聞けるようになるのが、だいたい3学期だったのです。そんな繊細くんも、今では初めて遊ぶ友だちだったとしても、事前に「どんな子?」「どんな顔?」「どんなものが好き?」を〝見える化〟したプロフィールシートのようなものを作って見せておいてあげると、安心もするし、相手に興味も湧いて、「はじめまして」でも楽しく遊べるようになりました。
心と脳を伸ばす関わりで、初めてのことを許容できる力が伸びているのです。
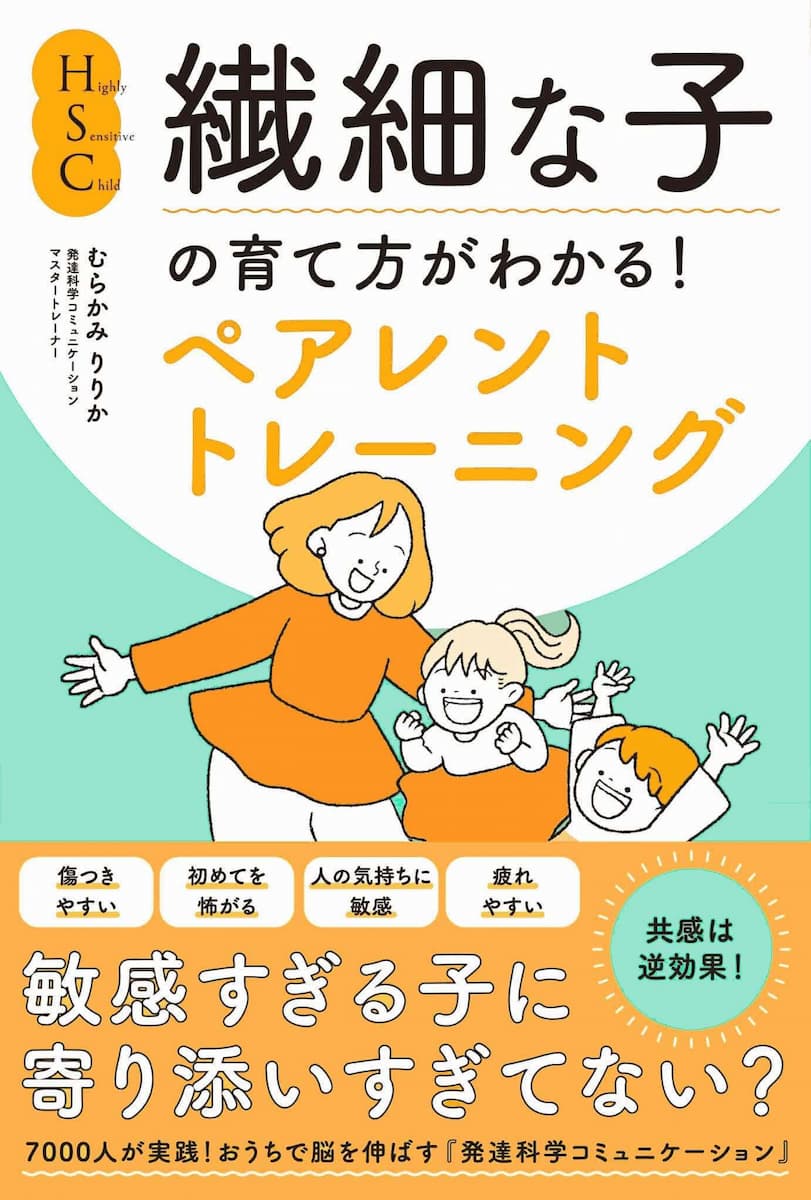
むらかみりりか『HSC・繊細な子の育て方がわかる!ペアレントトレーニング』(パステル出版)
「共感は逆効果だった――」
「初めてのことが苦手」「学校に行くのがつらい」「すぐ傷つく」そんな繊細な子が、わずか3カ月で笑顔で挑戦できる子に変わった!繊細な子の脳を発達させる、親子のコミュニケーションの新常識がわかります。
本書は、脳科学に基づいたペアレントトレーニングを通じて、親の関わり方を変えるだけで子どもが大きく変わった理由と解決策を、親子の実話とともにまとめた一冊です。































