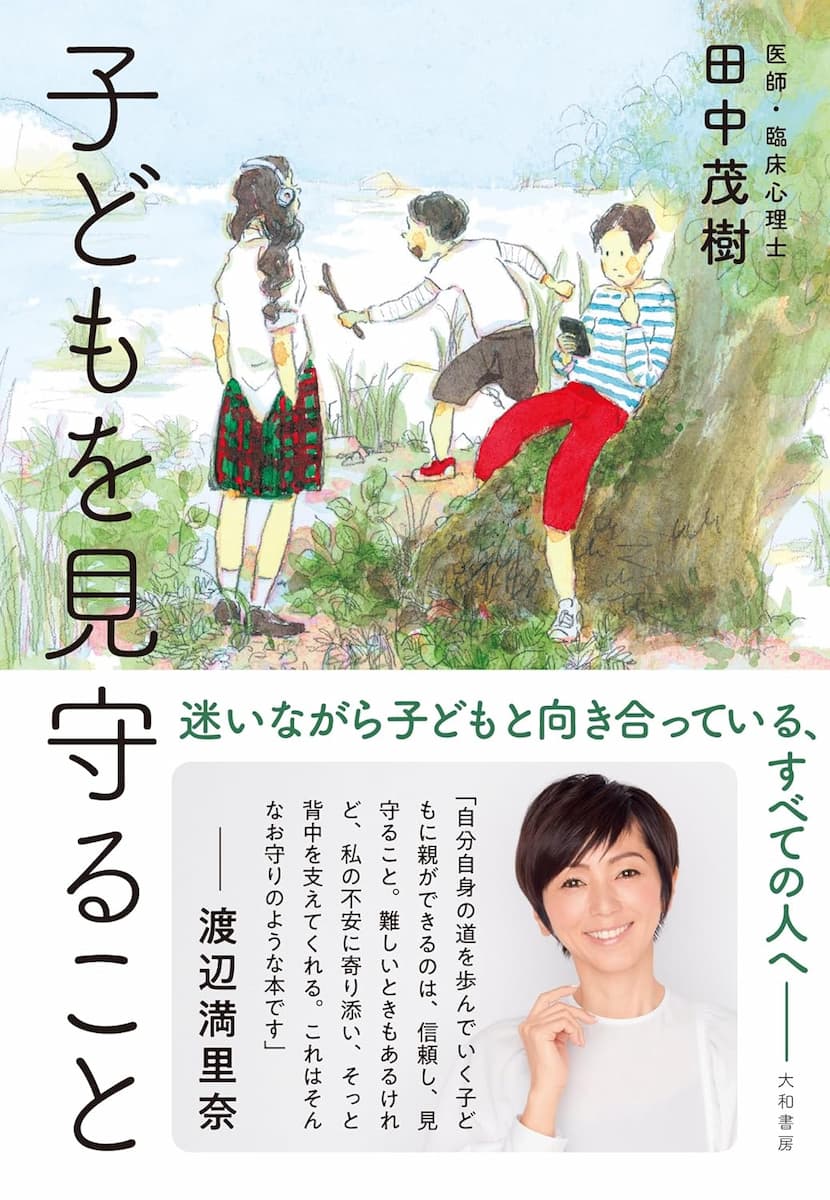口うるさいと親も子も疲れる?「小言をやめる」ことのハードルとメリット
「ちゃんと宿題しなさい」「スマホばっかり見てないで」と、気づけば一日に何度も口にしている、子どもへの小言。「言わなきゃ伝わらない」と思いがちですが、医師で臨床心理士の田中茂樹先生は、実は小言を言わないことにこそ多くのメリットがあると語ります。
その理由について、著書より抜粋してご紹介します。
※本稿は田中茂樹著『子どもを見守ること』(大和書房)より一部抜粋、編集したものです。
小言を言わないこと
小言を言わないことは、私がカウンセリングで軸としている方針のひとつです。ほかには「子どもにとっていちばん大事なのは、家でリラックスすること」というのもあります。小言を言われてはリラックスできないので、これらはたがいに関係があります。
小言を言わないこと―は、子どものそのままの姿を受け入れるというメッセージになります。小言は相手の気に入らないところを指摘する言葉です。アドバイスというと少し前向きな印象になりますが、やはり、「今のあなたは、ここがよくない。ここが足りない。だから、それを直すともっとよくなるよ」というメッセージです。
クライアントから子育て相談を受けた際、相談の内容がどうであれ、面接では小言を控えて子どもに接してみることを勧めます。そうして自分や子どもに起こる変化を感じてみましょう、と。
とはいえ、小言を控えるのは、実は、とても難しいことです。それまでの習慣を変えることは簡単ではありません。それを、覚悟を決めてやることで、多くの場合、子どもに明らかな変化が起こってきます。親は体験したことを、面接で話してくれます。
「今までと違って、子どもが食事のあともリビングにいるようになりました」
「スマホを、自分の部屋ではなく、リビングのソファでやるようになりました」
「キッチンで私のそばに寄ってきて、友だちのことや学校のことを話してくれるようになりました」
「よく笑うようになりました」
こういう話が面接で聞かれると、この人はがんばっているんだなと推測できます。
子どもに変化が起きるのはなぜか。子どもは、嫌なことを言われないと分かると、親と話がしたいし、一緒にいたいと思うようです。大人と違って、子どもは柔軟性が高いので、変化もわりとすぐに現れてきます。もっと言えば、小言を言わないでいいとなると、親も楽になるのです。親としてしっかりしていないといけない、そういう制約から解放されて、親も子どもとの時間をリラックスして過ごせるようになるのです。その親の変化を、子どもはすぐに感じ取ります。
子ども時代を思い出せば
小言を言われないことの快適さは、自分が子どもだったときのことを思い出せばよく分かると思います。たとえば、家庭科の授業で、手さげ袋を縫った。自分としては、うまくできて先生にもほめられた。それを持って帰って親に見せた。すると、「あら、よくできたわね。でも、ここがちょっと残念だったね。ほら、模様がズレちゃってるでしょ。今度は、こうやったらもっとよくなるよ」などと言われてしまって、がっかりした。そんな経験はないでしょうか。
親としては、悪気はまったくないのです。親から見れば、子どものやることには、いろいろと足りないところがある。そして、少しでも上達・成長してほしいと思って、どうすればもっとよくなるかを伝えようとします。それはもしかしたら、その先の子どもの人生で役立つ場合もあるかもしれません。
しかし、子どもからしたら、できていないところを指摘されて、「そのままではダメだよ」と言われた気分になるでしょう。自分としては、うまくできた、ほめられてうれしかった。だからそれを大好きな親に話した。一緒に喜んでほしいのです。親からの、「話してくれて、見せてくれて、ありがとう」という反応こそ、子どもの望んでいることでしょう。
小言を言ってはいけないのですか? という質問
このように講演で話すと、「では子どもに小言は一切言ってはいけないのですか?」「アドバイスもダメなんですか?」「そんなことでは、子どもは成長しないのではないですか?」「親としての役割、子どもを導き育てる役割を放棄していることになりませんか?」などのコメントを必ずもらいます。
小言やアドバイスを言ってはいけないと言うつもりはありません。アドバイスをして子どもを伸ばしてやりたいと思うのは、親として当然です。それは親の大事な務めでもあるでしょうし、喜びでもあるでしょう。そこに異論はありません。ここで述べたいのは、小言を言わないことには前向きな意味がある、ということです。
指摘すべき問題があるのに言わないのは、子どもを放置していることになるのではないか、親としてすべきことをやっていないのではないか、というような不安を持つ人がいます。その一方で、次から次へとアドバイスを与えながら、それらのアドバイスは、子どもの幸せに役に立つ、しっかり届ければ届けるほど良い、ということを疑っていないような人がいます。
そのような人にこそ、小言を言わないことには実はメリットがあるということを伝えたいのです。小言を言われずに家庭でリラックスして過ごせることは、子どもの幸福ですし、子どもが幸福であることは、親も幸せにします。これは、とくに費用もかからない、それでいて効果のある「幸福をもたらす」方法です。
今までなぜあんなに小言を言っていたのだろう
小言を意識してやめてみると、多くの親は、これまで自分はなんと多くの小言を言っていたのかと気がつき驚きます。そして、自分の関心が子どもの至らないところにばかりに向いていたんだな、ということにも気がついていきます。言葉はよくないですが、いわば、あら探しばかりしてきたようなものです。そこを、意識して抑えてみる。それは“小言依存症”からの離脱を目指すものです。
小言依存症から脱することができると、今まで見えていなかった子どもの部分が見えてきます。たとえば、子どもがどう考えて行動しているのかを発見できることもあるでしょう。それまでは子どもの考えが理解できず、ただ無意味な行動をしているように親には見えており、小言を言ってしまっていたかもしれません。でも、実はその小言は必要がなかったのだ、というようなことに気がつく。そういうことも起こってくるでしょう。
小言を控えることを心がけて、うまくできるようになってくると、親にも心の余裕が生まれます。この点こそが、小言を控えることにチャレンジすることの、最も大きなメリットです。子どものきちんとできていないところ、そこばかりに着目していた状態から脱出できるのです。
子どもが何を考えているのか、どう思っているのか、それが見えてくると、子どもといることが、楽しくなってきます。余裕を持って見守ることができるようになってきます。もちろん親の気分は楽になります。親の表情や声がやわらかく、やさしくなると、子どもはもっとリラックスしていきます。親に話しかけたいという思いもでてきます。家全体のコミュニケーションが以前よりも楽しい、温かいものに変わっていきます。
小言を控えることに挑戦してみた親が、よく口にするのは次のような言葉です。
「うちの子は、私が思っていたよりも、ずっとしっかりしているんだと気づきました」
「子どもが話してくれているのを、遮らずに聞いていたら、ふと昔の自分を思い出しました。そういえば、こうやって私も親に話していたなぁって。何十年ぶりかで、思い出しました」
「いろいろとうるさく言ってきたけれど、どれも必要なかったんだなと分かりました。あんなふうに小言ばかり言われて、あの子はつらかっただろうなと思います。それなのに、私のことを好きだと言ってくれます。幸せなことだと思います」
一日だけでも挑戦してみてください。
田中茂樹著『子どもを見守ること』(大和書房)
本書は、医師・臨床心理士として20年以上にわたり多くの親子の相談を受けてきた著者が、「子どもを変えようとするのではなく、信じて見守ること」こそが、子どもの心を育て、親自身をも楽にするというメッセージを、豊富な実例と共に伝える一冊です。