「お母さんは、弟ばかりかわいがる」弟を持つ姉が感じる不平等の正体
弟のいる長女は、「母は弟にばかり甘い」と不平等さを感じがちです。しかし、その背景にあるのは愛情の差ではなく、こどもの性質に合わせた接し方の違いかもしれません。
弟のいる長女の心理と、親が気をつけたい関わり方について、潜在意識の専門家・谷原由美さんの著書よりご紹介します。
※本稿は、谷原由美著『子どもの心に自信のタネをまく方法』(青春出版)より一部抜粋、編集したものです。
弟のいる長女さんの育て方
同じ長女とはいえ、下に妹が生まれるか、弟が生まれるかでは、つくられる潜在意識が変わります。
弟のいる長女さんの中には、「お母さんは、弟ばかりかわいがっていた」と思って育った方が多いかもしれません。
でも、それは、子どもの男女差とそのシチュエーションからくるもので、実は親のせいではないことがほとんどです。
子どもとはいえ女の子は、男の子に比べてしっかりしていて、早く成長します。言葉も早く、理解力も早くて、お母さんの話をきちんと聞きます。
それに比べて男の子は、まったく違います。
最初の子どもが女の子で、次が男の子だった場合、たいていの親はびっくりします。とくに性別が違う母から見ると、「宇宙人が生まれてきた」というほど、男の子というものは、理解不能な生き物なのです。
車や電車などに異様に興味を持ったり、予想外の動きをしたりします。遊ぶときも擬音語で「ガガガ……」とか「クシャッ」とか「ビシッ」などと言ったりして、もはや言葉ではありません(笑)。
女の子はそんなことはありません。ちゃんと言葉を話します。お母さんにとって男の子は驚くことばかり。言ってもわからない、理解しない、この連続なので、お母さんは男の子に対してどうしても大目に見ることが多くなります。
たとえばお姉ちゃんには「甘いものばかり食べちゃダメ」と言っていたのに、弟には何も言わずに食べさせている。
これを見て、お姉ちゃんのほうは「私のときはダメって言ったのに」と思うのです。「なんで弟は大目に見られているのか」「なんで甘く育てられているのか」「ずるい」と、とても嫉妬するのです。
お母さん(お父さん)からすると甘く育てているのではなく、しつけをあきらめた状態です。
頑張ることをしなくなることも
ここでお姉ちゃんは、「ものわかりのいい私では厳しくされるばかりなので、頑張るのはバカバカしい」と思うようになります。つまり、頑張らなくてもかわいがられる弟を見て、一生懸命頑張ることをやめてしまうのです。
第1子は基本的に素直なお子さんが多く、親の言うことに実直で、頑張るタイプです。
それは、生まれてから第2子が生まれてくる間、親が自分だけを見てくれている期間が必ずあるから。これは第1子だけの特権ともいえるもの。ほかのきょうだいがいないので、必ず「私と親」だけの世界があり、それが潜在意識に影響します。だから親を大事にします。
ところが下の子が生まれた途端、世界が一変してしまいます。ましてや男の子だと、お母さんの態度が自分のときと明らかに違う。だからこそ、弟がずるいと思ってしまうのでしょう。全員がそうではありませんが、そのような傾向があります。
あるいは、自分はダメだと思ったり、自分は愛されないと思ったり、自己肯定感が低くなることもあります。
そうした思いを持ちながら育つと、大人になって頑張らないといけないような場面がくると、なんだかやりたくなくなるとか、何かがうまくいきそうになるとチャンスを逃してしまう、などということになりかねません。
弟のいる長女さんは、気さくで親しみやすい感じに育ちます。「うまくいくだけが人生じゃないよ」といった達観した感覚を持ち合わせているのです。ボケやツッコミも上手で、冗談がわかる人も多いです。
弟のいる長女さんを育てるときは、弟に嫉妬をすることのないように注意を払ってみてください。どうしても弟を大目に見てしまうのはわかりますが、物わかりのいい長女さんが物わかりが悪くなりだしたら、それがサインです。
心が満たされれば大丈夫
下の子が生まれても、お姉ちゃんには変わらぬ愛情を注いであげることが、何よりも大切です。手がかかる弟の世話はしなければなりませんが、心だけはずっとお姉ちゃんのほうに向けてあげることです。
難しいことではありません。できるだけそばにいて、お姉ちゃんがお人形で遊んでいたら、「楽しそうね」と言うだけ、テレビを見ていたら、「面白いね」と言うだけでいいのです。
たとえば、長女さんがペットボトルのキャップを一人で開けられたので、嬉しくてお母さんのほうを見たら、お母さんは弟の世話が忙しくてまったく見てくれなかったとします。
子どもはただ、「お母さん、見て!」と言って、できたことを共有したかったのです。
このときお母さんが弟の世話をしていてもすぐ隣にいて、「できたね」と言ってあげられていたら、それだけで長女さんの心は満たされるのです。
心が満たされれば、心が荒れることはありません。見てくれないから、「ねえ、見て、見て!」という激しい主張が始まるのです。
子どものことを関心を持って見ていたら、自然に話しかけますよね。要は、お姉ちゃんの気持ちと一緒にいればいいだけです。
小さな弟は、抱っこしているだけで十分。1歳くらいまでの下の子の世話はオプションくらいの気持ちで、上の子メインでいきましょう。
一度きちんと赤ちゃん返りをさせてあげて「お姉ちゃん、いつもありがとう」と伝えてあげてくださいね。
長女さんとは友だちのような心の交流をしていくといいのです。
親だからと思って指導するような気持ちになると、第1子の女の子はすごく反発するでしょう。
とくに弟が生まれた後は、指示されることが自己否定されているかのように感じるため、上から話す、指導する関係をやめて、共に育つ、友人、同志のようになると、よく考える子になり、お子さんの知恵も能力も高まっていきます。
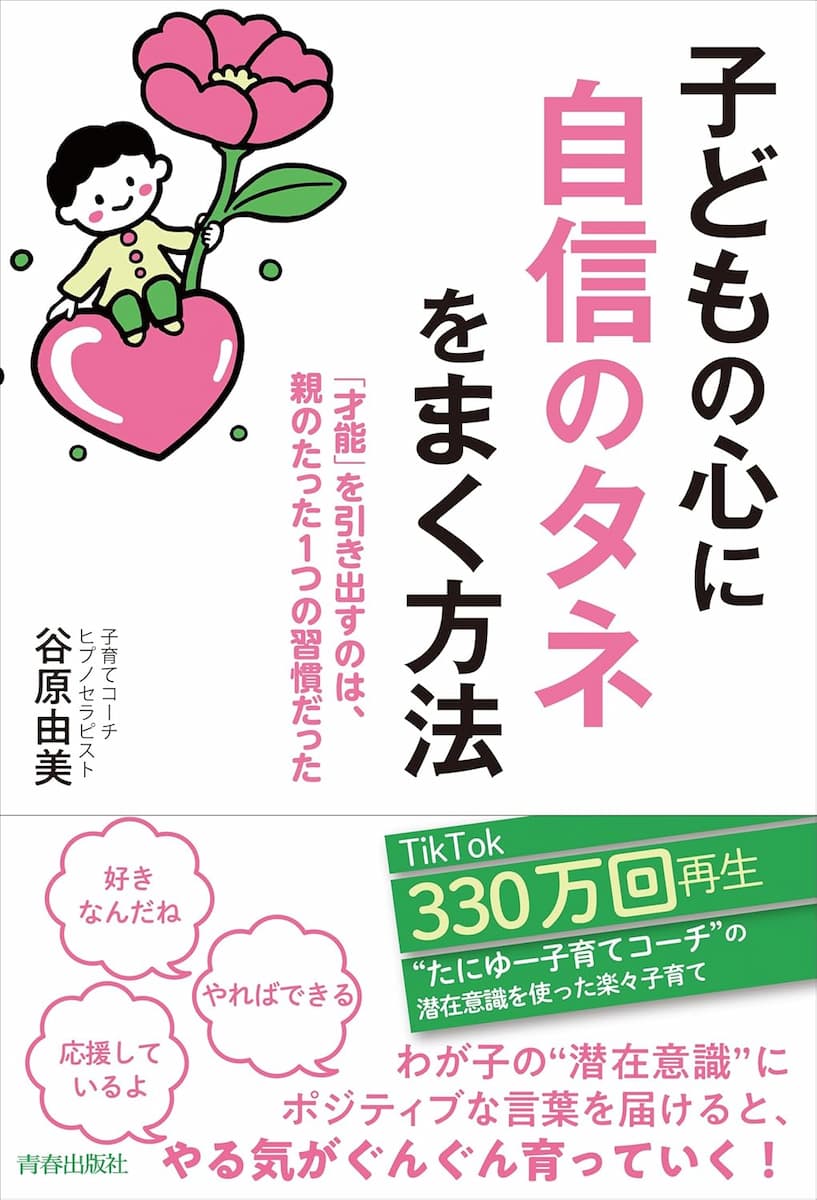
谷原由美著『子どもの心に自信のタネをまく方法』(青春出版)
10歳までで決まる!子どもの隠れた才能を引き出す親のたった1つの習慣とは?TikTok330万回再生の人気子育てコーチたにゆーが教える、潜在意識を味方につけて子どものやる気と才能を伸ばす子育て。