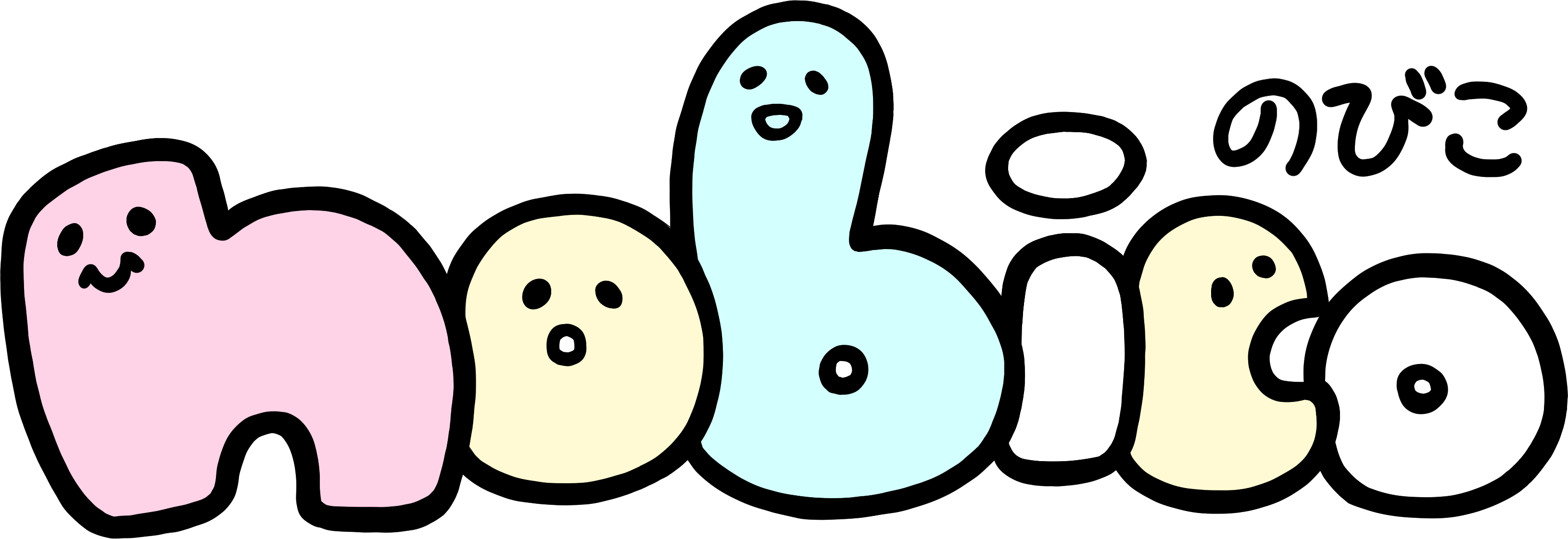「塾講師に子どもの話をペラペラ話す母」に届かなかった中学受験生の本心

首都圏模試センターの調べでは、2023年の中学受験者数は過去最多。2024年はさらにそれを超え、史上最多数を更新する見込み。親の受験熱は沸騰する一方です。
しかし、子どもたちは本当に受験をしたいと思っているのでしょうか? 必死の勉強の末に合格を掴み取ったとして、本当に充実した学生生活を送ることはできるでしょうか?
作家の尾崎英子さんは子どもの中学受験に伴走した経験から、4組の親子の受験物語を描いた小説『きみの鐘が鳴る』を発表しました。家庭環境や個人の特性からそれぞれの受験エピソードが描かれています。
本記事では、5年生の3月に塾を変わりたいと言う子どもに不満げな母親と、その母に苛立ちや不安を抱く子どもの心情を描き出すシーンを紹介します。
※本記事は尾崎英子著『きみの鐘が鳴る』(ポプラ社)より一部抜粋・編集したものです。
尾崎英子(おざきえいこ)
1978年、大阪府生まれ。早稲田大学教育学部国語国文学科卒。2013年『小さいおじさん』(文庫刊行時に『私たちの願いは、いつも』に改題)で第15回ボイルドエッグズ新人賞を受賞しデビュー。将棋を指せるカフェに通う六年生の少女の成長を描いた『竜になれ、馬になれ』(光文社文庫)もいくつもの模試に使用された。
試験が終わってから思い出すテストの答え

鉛筆を持ったまま頬杖をつき、窓の外を見た。のっぺりと塗ったような灰色の空を、電線ががんじがらめに縛り付けている。さっさと終わらせて、家に帰りたい。つむぎは顔を前に向けて、ホワイトボードの上の時計を見た。
終了時間まで3分くらい残っていた。これでいい、とは思ったけど、この塾に入れてもらえなかったら、また違う塾のテストを受けなくてはならない。それは嫌だからもう一度見直すことにする。
『豊田市や日立市のように、大企業を中心に関連企業が集まり、発展していった工業都市のことを漢字五文字で答えなさい。』
何だったかな。お城のそばに町ができるようなものだと教わったことは思い出せたが、漢字五文字が浮かばない。『城』と書いてみるが後の四文字が埋められず、それも消して白紙にした。
社会なんて、覚えているかどうかなので、わかるものはわかるし、わからないものはいくら考えてもわからない。ア、イ、ウ、エの中から正しいものを一つ選びなさいという問題。四問中、すべて『イ』っていうのは、ちょっと不自然だろうか。でも、どれも『イ』のような気がするんだよね……。
「はい、終了です」
教壇の横に座っていた女性の先生の声で、つむぎは鉛筆を置いた。数秒前には、これでいい、と思ったくせに、終わってしまうと未練がましく書き終えた自分の字を眺めてしまう。
学校の教室の半分ほどしかない部屋には、机と椅子のセットが20ほどあるが、そこにいる生徒はつむぎ一人だ。先生は、すぐに答案用紙を取りにきた。

あっ、城下町! 答案用紙を回収されたとたん、頭に浮かんだ。そうだ、『企業城下町』じゃん。ちゃんと五文字だし。ああ、もうダメだ。この塾にも入れないかもしれない。そう思ってしかめっ面になったのも一瞬で、たった一問だし、まあいっか、と思う。
「これで、四教科のテストは終わりました。疲れたかな」
その人の胸元の名札に『五十嵐』と書かれている。『いがらし』と読むらしい。テストがはじまる前に、そう紹介された。
「ああ、まあ」
つむぎはあいまいに頷く。
「お母様は二階でお待ちだから、荷物を持って下りましょう。忘れ物のないようにしてくださいね」
リュックの中にペンケースと問題用紙を押し込んで、椅子の背にかけていたジャンパーを羽織る。教室を出る前に、あらためて室内を見回した。狭くて、地味。もしも今日のテストで合格点を取れたら、ここに通うことになるのか。
3年生の終わりから通っていた東研フロンティアを自分からやめたいと言い出したのだが、こうして他塾と見比べると、それまでいた場所が良いところに思えてしまう。
暖房のきいた部屋から出ると、廊下が寒く感じられた。今日から3月になるのに、まだ春は遠そうだ。