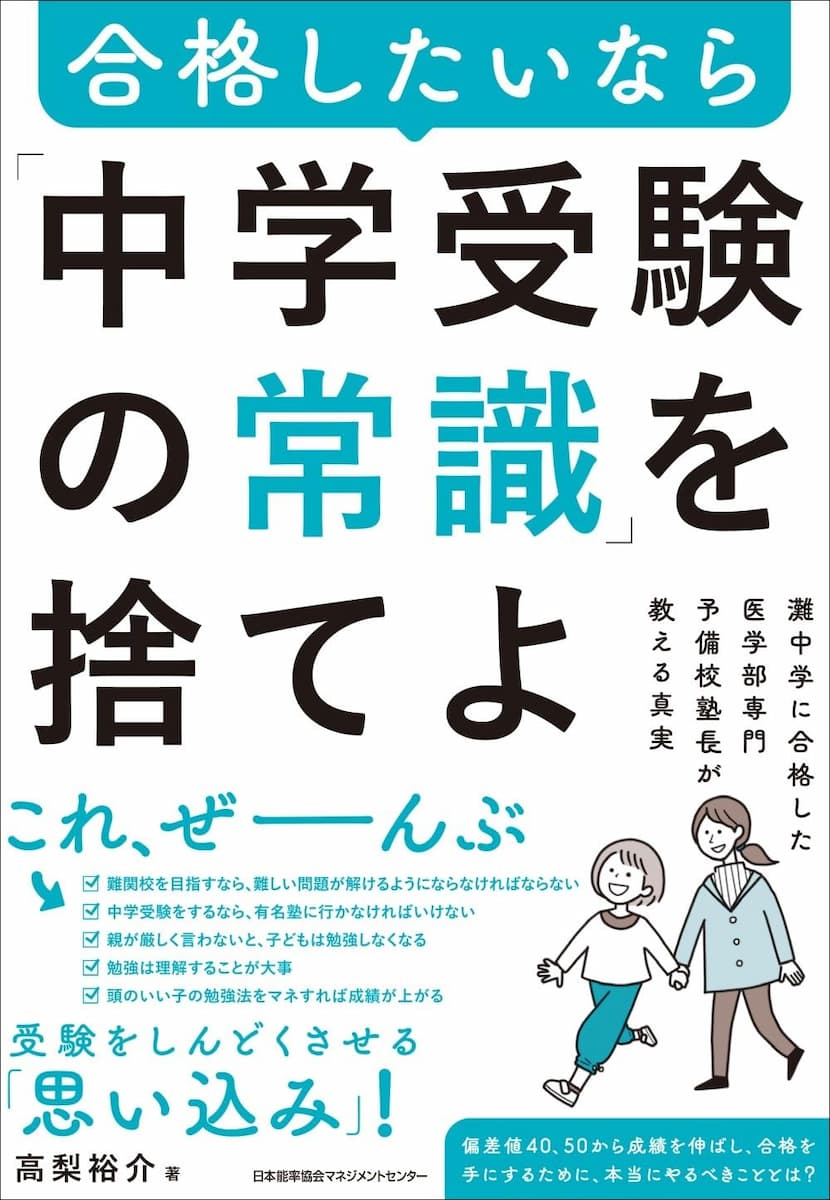「理解不足だから成績が下がる」わけではない? 受験勉強で陥りがちな思い込み
「前回より成績が下がった…」 そんなとき、「もっと理解を深めなければ」と考えていませんか? しかし、成績が下がる本当の理由は、“理解不足”ではなく、“基礎の抜け”にあります。
授業の解説を聞いて「分かったつもり」になっても、実際にテストで解けなければ意味がありません。
難しい問題の理解に時間をかけるより、基礎の抜けを埋め、何度も繰り返す学習が、最も確実に成績を上げる方法です。
本記事では、成績が下がる本当の理由と、すぐに実践できる「基礎の定着法」をお伝えします。
※本稿は、高梨裕介 (著) 『灘中学に合格した医学部専門予備校塾長が教える真実 合格したいなら「中学受験の常識」を捨てよ』(日本能率協会マネジメントセンター)から一部抜粋・編集したものです。
×暗記を後回しにする
〇暗記にこそ時間をかける
理科の入試問題には、植物や動物、星の種類など、単純に暗記をすればいい分野と、水溶液やテコのように計算式を使って解かなければいけない分野があります。
どちらも入試に出題される大事な分野ですが、塾の授業で時間をかけるのは後者です。
なぜなら、塾の先生が「解説」しやすい分野だからです。
この「解説」こそが、塾の「授業」で、これを行うために塾はお金をもらっていると言ってもいいでしょう。
でも、私はそこにあまり価値はないと思っています。
なぜなら、教科書ワークを使えば、これらはすべて書かれているからです。
しかも、人が口で説明するよりも論理的に書かれているので、とても分かりやすいのです。
ならば、その解法をそのまま覚えて、習得すればいいだけのこと。
つまり、暗記をすればいいのです。
ところが、多くの人は、この「暗記」を軽く見ているように思います。
植物や動物などの生物分野は、あとで暗記をすればいいだろうと後回しにして、「考えなければいけない」と思い込んでいる問題ばかりに時間をかけてしまっているのです。
そのほうが難しい勉強をやっている気分になるし、一生懸命に考えているふうの姿は、端からは頑張っているように見えます。
でも、これまで何度もお伝えしてきたように、「授業を聞く」というのは、めちゃくちゃラクな時間なのです。ただおとなしく聞いていればいいのですから。
難しい問題を前に頭を抱えているのも同じです。考えているつもりになっているだけで、実際は頭が働いていないのですから。
でも、暗記は違います。頭をフルに回転させなければいけない。
では、もし「いまからここにあるメニューと値段を20個全部覚えてください。5分後にテストをします」と言われたら、どうしますか?
メニュー名を隠すなり、値段を隠すなりして、とにかく覚えると思います。
ここで、「なんでこのメニューはこの値段なのだろう?」なんて理屈は考えず、ただただ必死に覚えると思います。
これってめちゃくちゃ頭に負荷がかかりますよね。
暗記をするとは、そういうことです。
つまり、ちっともラクじゃないし、めちゃくちゃ大変なのです。
しかも、覚えてもすぐ忘れてしまうのが人間です。
だから、何回も復習して覚えなければいけない。
余裕ぶって、「あとでやればいいや」なんて言っていたら、入試には間に合いません。
新しいことを学んだら、すぐ覚える。そして、何度も繰り返し覚え、アウトプットして定着させていく。
これが「暗記」であり、「習得」です。
そして、この勉強法がいちばん得点力を高め、テストや受験に有効なのです。
×いくつもの問題集に手を出す
〇同じ問題集を5周する
問題集は1回やって終わり、ではありません。
1回やっただけで全部覚えられる人がいたら、それこそ天才です。
2周やっても、まだ「抜け」はたくさんあります。
私は、3周、もしくは4周、多くの場合は5周以上やってようやく定着すると考えています。
問題集をやり込むとは、そのくらい大変なことなのです。
ただ、ここで一つ疑問が上がると思います。
何回も、何回も繰り返すことが大事、それは分かるけれど、同じ問題集を使い続けていたら、「さすがに全部の問題を覚えてしまっているから意味がなくない?」ということです。
実はこれに対しては、私も不確かだった時期がありました。
医学部受験では1浪や2浪する人は少なくありません。
私の塾でも残念ながら1年目は不合格で、2年目を迎えた生徒がいました。
1年目の途中から大手予備校から転塾してきたため、問題集を3周回した段階で入試本番に。まだ抜けが残っていたのが不合格の原因でした。
あと1年同じ問題集を使うべきか、別の問題集に変えてみるか迷ったのですが、本人が「もう1年あるのなら、まっさらな気持ちで別の問題集で勉強したい」と言うので、問題集を変えてみることにしたのです。
すると面白いことに、結局前に使っていた問題集でできていた問題は、新しい問題集の類題でもできて、できていなかった問題はできないということが分かったのです。
つまり、問題集を変える意味はなかったということです。
むしろ、新しい問題集に変えると、はじめの1周はやっぱり時間がかかります。 全教科をやるとなると2〜3か月かかってしまうのです。
これを2周、3周、4周やるとなるとかなりの時間を費やしてしまうことが予測できました。
もしかすると、3周くらいで入試本番を迎えることになってしまうかもしれない。
それでは、問題集をやり込むという状態とは言えません。
でも、もともと使っていた問題集なら、すでにできている問題はたくさんあるし、できていないところはまだできていないとすぐに気づけるので、対策がしやすい。
そこで急遽、もとの問題集に戻すことにしたのです。
すると、1年目に入塾した段階では偏差値40台だったのが、2年目で偏差値68まで跳ね上がり、志望していた医学部へ合格。
1年目の不合格は、単に繰り返しが足りなかっただけで、難しい問題の勉強をしてこなかったから不合格になったわけではなかったということが証明されたのです。
たくさんの問題集に手を出すのは、一見たくさん努力したように見えますが、実は効率の悪い学び方。
貴重な時間を無駄にしないよう、正しい努力を積み重ねていきましょう。
×成績が下がったのは理解不足だったから
〇成績が下がったのは基礎が抜けてしまったから
テストや模試の成績は、過去の勉強の積み重ねを一時的に数値化したものに過ぎません。同じ点数を取っても、テストを受ける母集団が変われば偏差値が下がることは当然起きるし、たまたま苦手な分野が出てしまったり、うっかりミスをしてしまったりして点数を落としてしまうこともあります。
なので、一喜一憂する必要はありません。大事なのは、そのあとです。
テストや模試が悪かったとき、まずはその原因を探る必要があります。
このとき、多くの人は「成績が下がったのは理解不足だったから」と思い込み、できなかった問題の解説を読んで理解しようとします。
ここで「あ、そういうことか」と理解できれば、一件落着にしてしまう。
もし解説を読んでも分からなければ、先生に質問しに行くなどして、なんとか理解しようとします。
そして、説明を聞いているうちに、理解できた気になってしまうのです。
だけど、成績が下がった本当の理由は違います。
「理解不足だったから」ではなく、単に「基礎が抜けていた」ことが原因です。
覚えていたことをうっかり忘れてしまった、あるいは前は覚えていたのに、時間が経って記憶が曖昧になってしまった、テストの範囲が広がったことで全部が覚えきれなかったなど、結局は「覚えていなくて成績を落としてしまった」のです。
だから、きちんと覚えさえすれば、成績は絶対に上がります。
このように、成績が下がる理由はとてもシンプルなのに、それに気づいていない人が多いのです。
そして、「難しい問題の理解」といった間違った勉強ばかりに力を入れてしまう。
だけど、中学受験、さらには医学部受験において、難しい問題の理解はまったく不要であることが分かっています。
むしろ、難しい問題を正解させるために多くの時間を取られ、みんなが正解できる基礎問題でぽろぽろ取りこぼしがあっては意味がありません。
成績を確実に上げる方法は、基礎の暗記と習得を行うことです。
『灘中学に合格した医学部専門予備校塾長が教える真実 合格したいなら「中学受験の常識」を捨てよ』(高梨裕介 著/日本能率協会マネジメントセンター)
今までの「中学受験の常識」が合格を遠ざけている?!
高偏差値の大学に進学するには幼い頃から中高一貫校に入り、常に難問に挑み続けなければならないと思い込んでいる人が多くいます。
競争を煽る塾、甘やかしは悪とする親、管理至上主義……これらはすべて子どもの生きる力を奪います。
そんな負のスパイラルを断ち切るには、180度の意識改革が必要です。
実際、著者は毎年100 名以上の医学部合格者を輩出する医学部受験の専門予備校「エースアカデミー」を運営していますが、多くの受験生と面談すると、「しんどい」と深刻に悩んでいる相談のうち 6〜7割が親子関係の悩みだということがわかりました。
そこで子どもたちを悩ませる「親」の対応を改善するためには、間違った思い込みを正し、親が実施すべきサポートを体系化して伝える必要があるのでは、と感じるようになりました。
情報過多の現代社会においては、自分の子どもにあった学習方法よりも、世間一般によしとされている学習方法を盲信し、それが唯一の正解だと思い込んでいる親が多いのが現状です。
間違った学習方法や子どもへのかかわり方では、子どもの学力が向上しないばかりか、親からのプレッシャーで長年苦しむ子どもが増えるばかり。
本書では、受験生の親がすべきこと、すべきでないことを確認し、親が強いるのではなく、子ども自らが勉強に取り組むようになる行動変容を促すことで、受験を通して子どもたちが「自分軸」で生きていくベースを築き、かつ確かな学力向上につながる親の考え方と姿勢を提示します。