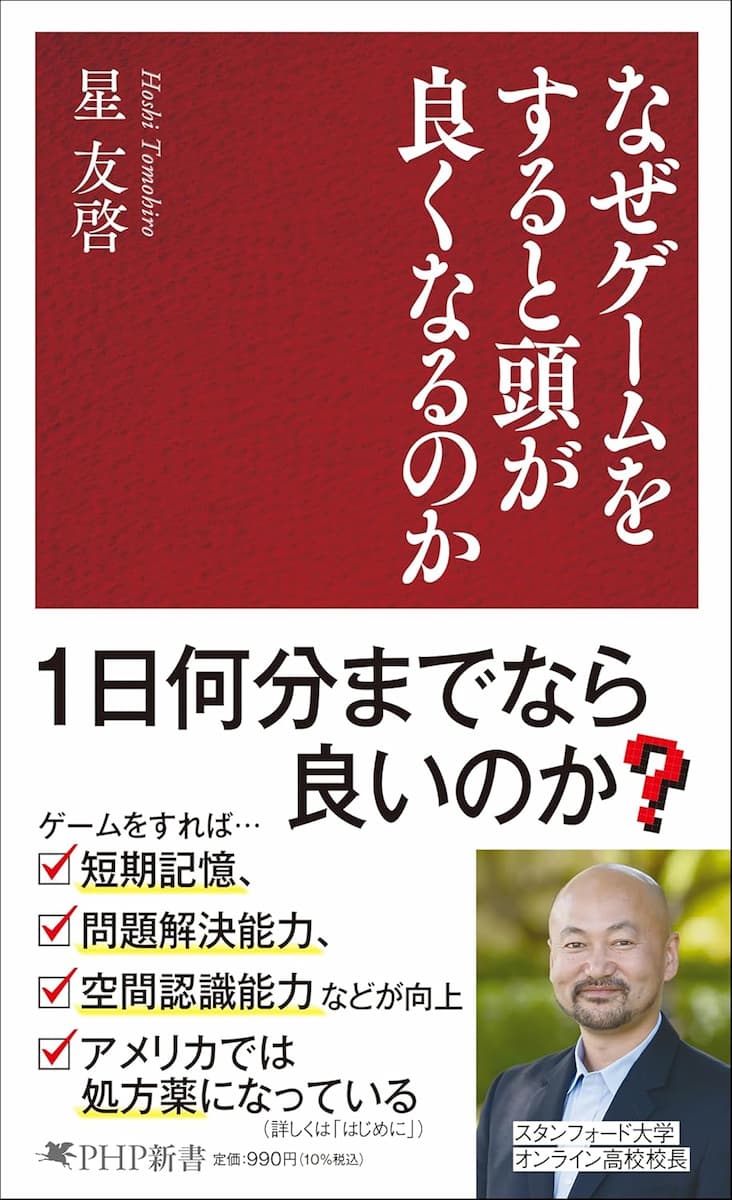“ゲームをやめない子”とどう向き合う? 親が見落としがちな「叱っても変わらない理由」と対処法

何かと問題視されがちなゲームですが、実は心の3大欲求である「つながり・できる感・自分から感」を満たせるというメリットも。小さな子どもを除き、1日平均2時間のゲームは脳にも心にも良い影響があるそうです。
しかし、2時間以上経っても、なかなかゲームをやめられない子は多いもの。そんな時、頭ごなしに「やめなさい!」と叱ってもあまり効果はありません。子どもがゲームと適切に付き合うためのコツを、スタンフォード・オンラインハイスクール校長・星友啓先生の『なぜゲームをすると頭が良くなるのか』よりご紹介します。
※本稿は星友啓著『なぜゲームをすると頭が良くなるのか』(PHP研究所)より一部抜粋・編集したものです。
「ゲーム禁止」は禁止

小さい子どもは極力避けて、学生や大人は2時間以下。しかし、ゲームプレーの時間がその範囲内で収まらないときにはどうしたらいいか?
まず、一気にゲームをやめさせようとしたり、無理やりゲームを遠ざけようとしてはいけません。
無理やり子どものデバイスを取り上げてゲームを禁止したり、自分自身に言い聞かせようと、あるときからパタリとゲーム時間を急激に減らしたりする。そういった「ゲーム禁止」アプローチは得策ではないのです。
「ゲーム禁止」がダメな理由は2つあります。まず、やめるべきことばかりにフォーカスが向かってしまうという点に注意しましょう。
たとえば、親が子どものゲームをやめさせようと、ついつい、
「今日はゲームやりすぎだから、もう終わり!」
「ゲーム依存症になっちゃうからやめなさい!」
「いったいいつまでゲームやってるの?」
などと、言ってしまいがちです。
こうした声かけは「やめるべきこと」や「ダメなこと」にだけフォーカスしてしまっています。
しかし、「もう終わり」「やめなさい」「いつまでやってるの」と言うだけでは、「ゲームはダメ」と拒絶するだけで、ゲームの代わりに何をすべきなのかを伝えていないことになります。
ここで重要なのは、ゲーム時間を減らそうとするときに、原点に立ち返って考えてみることです。ゲームの時間を減らさないといけないのはなぜなのか?
やりすぎで睡眠不足になり、食事もろくに摂らない、勉強などやるべきことをやらず、友人や家族関係もおろそかに。
ゲームではなくて、あるべき生活のバランスを取り戻すためにやるべきことがたくさんあるから、ゲームの時間を減らしたい。
そうであるならば、使用の制限をすると同時に、子どもたちがやるべきことを話し合っていかなくてはいけません。
だから、「ゲーム禁止」の声かけだけではなく、「生活バランス」の声かけに変えていく必要があるのです。
たとえば、
「ゲームばっかりやっていると運動できないから、外に遊びに行こう」
「ゲームもいいけど、やりすぎるとバランスが悪いから、違うことをやろう。何をやろうかな?」
など、子どもがやるべきことや、できそうなことを提案したり、何をするとバランスのいい生活になるのかを子どもと一緒に考えていくことが大切です。
自分自身でゲームをやめようとする場合も全く同じです。ゲームをやめることだけにフォーカスを置いてしまっては、ゲームをやらない分、代わりに何をしたらいいかがモヤッとしたままです。
そのため、ゲームをしない間の空白時間に、ついつい、ゲームのことを考えてしまえば、全くの逆効果です。
ゲーム以外にするべきことは何なのか? 何をやめるかということではなく、むしろ、その代わりに何をするかということにフォーカスする必要があるのです。
ゲームの代わりの見つけ方

それではゲームの代わりにどんなことをしたらいいのか?
「ゲーム禁止」がダメな理由の2つ目は、この問いに深く関係しています。
「ゲーム禁止」のアプローチがダメな2つ目の理由は、ズバリ、ゲームが私たちの心の3大欲求を満たしてくれるからです。
ゲームは「つながり」「できる感」「自分から感」をたっぷりと満たしてくれます。
それだけに、私たちの心の3大欲求は、ゲームに向いてしまっており、シンプルに「ゲームはダメ」と言ったり、自分自身で潔くやめようとしても、それだけではなかなかゲームから目を逸らすのは難しいのです。
さらに、ゲームを無理やりなくしてしまえば、それまでゲームをやることで満たされていた心の3大欲求を満たすことができなくなってしまいかねず、心にぽっかり穴があいてしまうかもしれません。
日常の中で満たすことができない心の3大欲求を、唯一ゲームが満たしてくれている状態だとしたら、そのゲームを突然やめてしまったり、取り上げてしまえば、心のリスクにさらされてしまう危険性だってあるのです。
それでは、どうしたら良いのか? ゲーム時間を減らそうとするときに、考えるべき重要なことは、ゲームの代わりに、心の3大欲求を満たしてくれるような活動を、新たに自分の生活のリズムに足していくこと。
「つながり」「できる感」「自分から感」をなるべく多く、深く満たせるような活動とゲームの時間を入れ替えていくのが大切です。
星友啓著『なぜゲームをすると頭が良くなるのか』(PHP研究所)
「ゲームなんて時間の無駄ではないか」と思っている人は少なくないでしょう。しかし、最新の脳科学や心理学の研究によると、ゲームにはさまざまな効用があるといいます。たとえば……。
■ゲームで海馬が大きくなって、活性化する
■アクションゲームは短期記憶、空間認識能力など理系の力を育てる
■マルチタスクの能力も上がる
■RPGやパズルゲーム、ストラテジーゲームで、問題解決能力が上がる
■「マインクラフト」などのサンドボックスゲームやパズルゲームで、クリエイティビティが上がる
■ゲームで脳が若返る
■メンタルや、周囲との関係性も改善する効果がある などなど……。
一方で、「ゲームをすると成績が下がるのではないか?」「暴力の原因になるのでは?」「集中力が下がってしまう?」と心配する人もいます。しかし、これまで行われた研究によると、ゲームをやりすぎてしまうと成績に悪影響が出てしまうものの、適度にやる分には影響はなく、むしろ、成績アップにつながる可能性も報告されています。そして、「ゲームをすると暴力的になる」「集中力が下がる」ということを示す信頼性の高いエビデンスは見当たりません。
では、「やりすぎ」にならない、適度なゲーム時間というのはどのくらいなのでしょうか? そして、ゲーム時間を無理なく減らしていくにはどうすればいいのか? 本書ではこうした疑問について、科学的エビデンスに基づいてアドバイスを行います。
本書ではそのほか、マインクラフトのメタバース空間を用いて、教育と医療を融合させる著者の取り組みや、ゲームを用いた治療法「DTx」(たとえば、アメリカの連邦機関であるFDAは「Zengence」というゲームを高血圧の治療法として認可しました)、ゲームによって授業や仕事の目的を達成しようとする「シリアス・ゲーム」など、ゲームの可能性を活用した新たな取り組みも紹介します。