才能より教育?親の熱心さがもたらす子どもの「将来の年収」への影響とは

みなさんのお子さんが大人になるまでにどんな教育ルートを通っていくかを想像したこと はありますか?2025年現在、子どもの教育にかかる費用は増加傾向にあります。少子化に伴い、子ども一人当たりにかける教育費の総額が上がっているのです。では、どうして人々はそこまで「教育」に躍起になるのでしょうか。
「教育」のもたらすものとは? 西岡壱誠(著)布施川天馬(著)『幼稚園から大学まで 勉強にかかるお金図鑑』から紹介します。
※本稿は、西岡壱誠(著)布施川天馬(著)『幼稚園から大学まで 勉強にかかるお金図鑑』(笠間書院)から一部抜粋・編集したものです。
教育のもたらす年収の上昇効果とは

例えば、ある会社に正社員として60歳の定年まで勤めたと仮定した場合、労働政策研究・研修機構による『ユースフル労働統計2022』によれば、男性の生涯賃金は中学卒で1億9000万円、高校卒で2億1000万円、高専・短大卒で2億1000万円、大学・大学院卒で2億6000万円になるといわれています。
また、女性は中卒で1億5000万円、高校卒で1億5000万円、高専・短大卒で1億7000万円、大学・大学院卒で2億1000万円となると推計されるそうです。このデータは、男女で賃金の差がありつつも、基本的には中卒よりも高卒が、それよりも大卒がより多くの賃金を得られることを示しています。
さらには、同じ大学卒の経歴でも、どんな大学を出たかによって、やはり生涯賃金の総額は大きく変化します。
東京大学卒業者の平均生涯年収は、コンサルティング会社AFGの推計(2017年)によれば、4億6126万円。
また、日経転職版の「大卒年収調査」で公開されているデータから推計すれば、早慶出身者もやはり4億円に迫る生涯年収を稼ぎだすと考えられます。
先ほど述べた『ユースフル労働統計2022』のデータでは、 大卒男性で2億6000万円、大卒女性で2億1000万円でしたから、同じ大卒でも2倍近くの差がついてしまうことがわかります。
日本は明らかに学歴社会です。特に大学の学部卒業までを人材判断の材料として著しく偏重し、「どんな大学を出たか」で年収が億単位で変動する。そのために、世の教育熱心な親御さんたちは、子どもに少しでも良い人生を歩ませるため、苦心して教育費を捻出するのでしょう。
才能はなくても教育の力で後付けできる

実際に、 教育熱心であることは子どものためになります。
青山学院大学安井健悟研究会が日本政策学生会議「政策フォーラム2017」のために作成した「親が子どもの将来の年収に与える影響」の中で、「親が教育に熱心であった家庭ほど、子どもの将来の年収に正の影響があった」と報告しています。
確かに、勉強ができるか否かでキャリアの大半が決まってしまう現状に対して、声を上げたくなる方もいらっしゃるでしょう。「勉強は才能だ」「地頭が良い人が勝つ」「地頭が遺伝するのだから、出来レースだ」と嘆きたくなる気持ちもわかります。
ただ、それはある意味で教育の敗北である気もしています。
私は教育を「才能によらず能力をたたき上げる外部からの圧力」であると定義しています。才能だけで勝ち抜いていける部分も間違いなくありますが、それに対抗するためにどんな練習の手法があるか、どんな技術があるか、どんな考え方、思考術があるか。これらを効率的かつ体系的に学ぶことができる場こそが、学校であり、塾なのです。
つまり、どんなに才能がなかったとしても、後付けの才能とも言うべき教育の力を頼れば、この学歴社会において、確実に上へとコマを進められると私は考えます。
親の価値観を押し付けないために

とはいえ、親の価値観の押し付けはよくありません。
実際に、先述した日本政策学生会議の調査によれば、「親の価値観の押し付け」すなわち「過度なしつけ」や「親が仕事に誇りを持ち、子どもにも同業を強要すること」などは子どもの将来の年収に負の影響をもたらすとされています。
金額やキャリアにもたらす影響だけではなく、子どもがどんなルートを選ぶか、親の価値観の押し付けにならない程度に話し合い、家庭内で対話することこそが、必要なのではないでしょうか。
キャリア選択の多様化が進む現代だからこそ、どんな道を選ぶか、しっかり検討すべきだと思います。
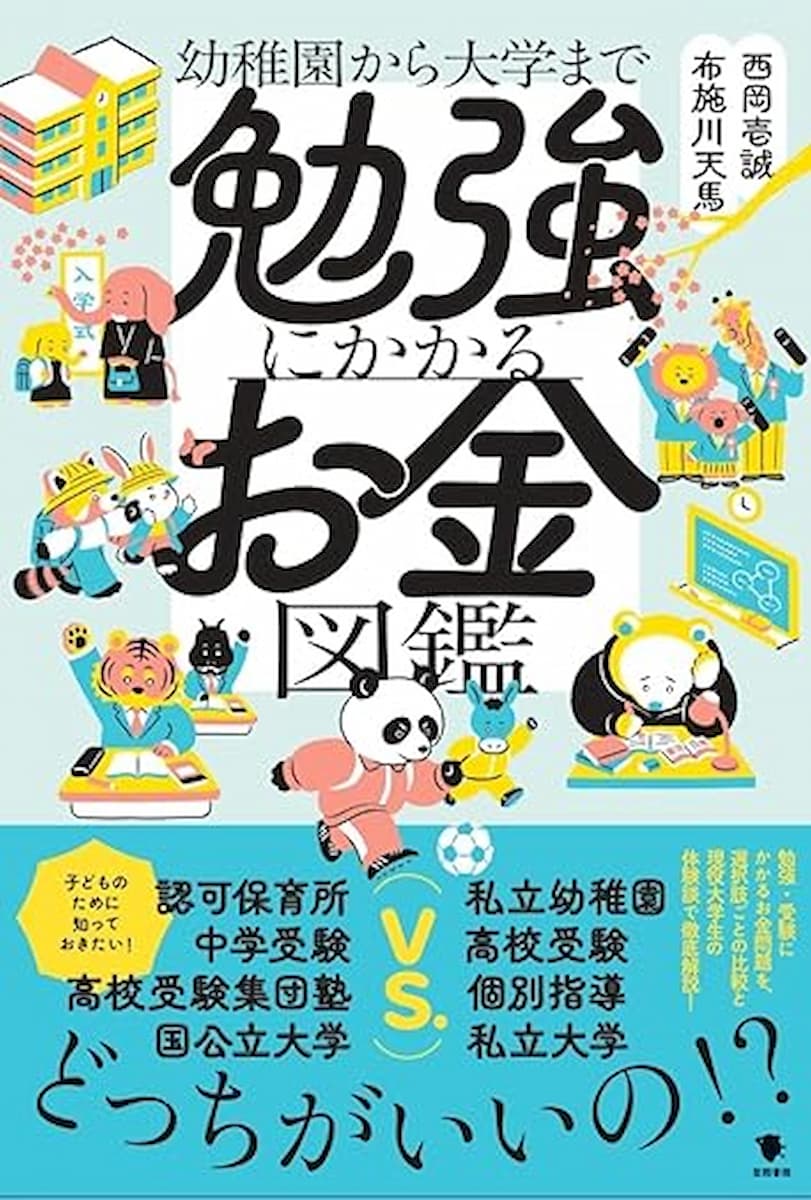
西岡壱誠(著)布施川天馬(著)『幼稚園から大学まで 勉強にかかるお金図鑑』(笠間書院)
塾・家庭教師・受験料・入学金……子どもの勉強や受験にはお金がかかります。本書は、累計50万部「東大シリーズ」著者で東大カルペ・ディエム代表・西岡壱誠と、貧しい家庭に生まれながら東大合格を果たした著者・布施川天馬が、「子どもの勉強・受験にかかるお金」の問題に特化し、経験と膨大なデータをもとにまとめた一冊です。
































