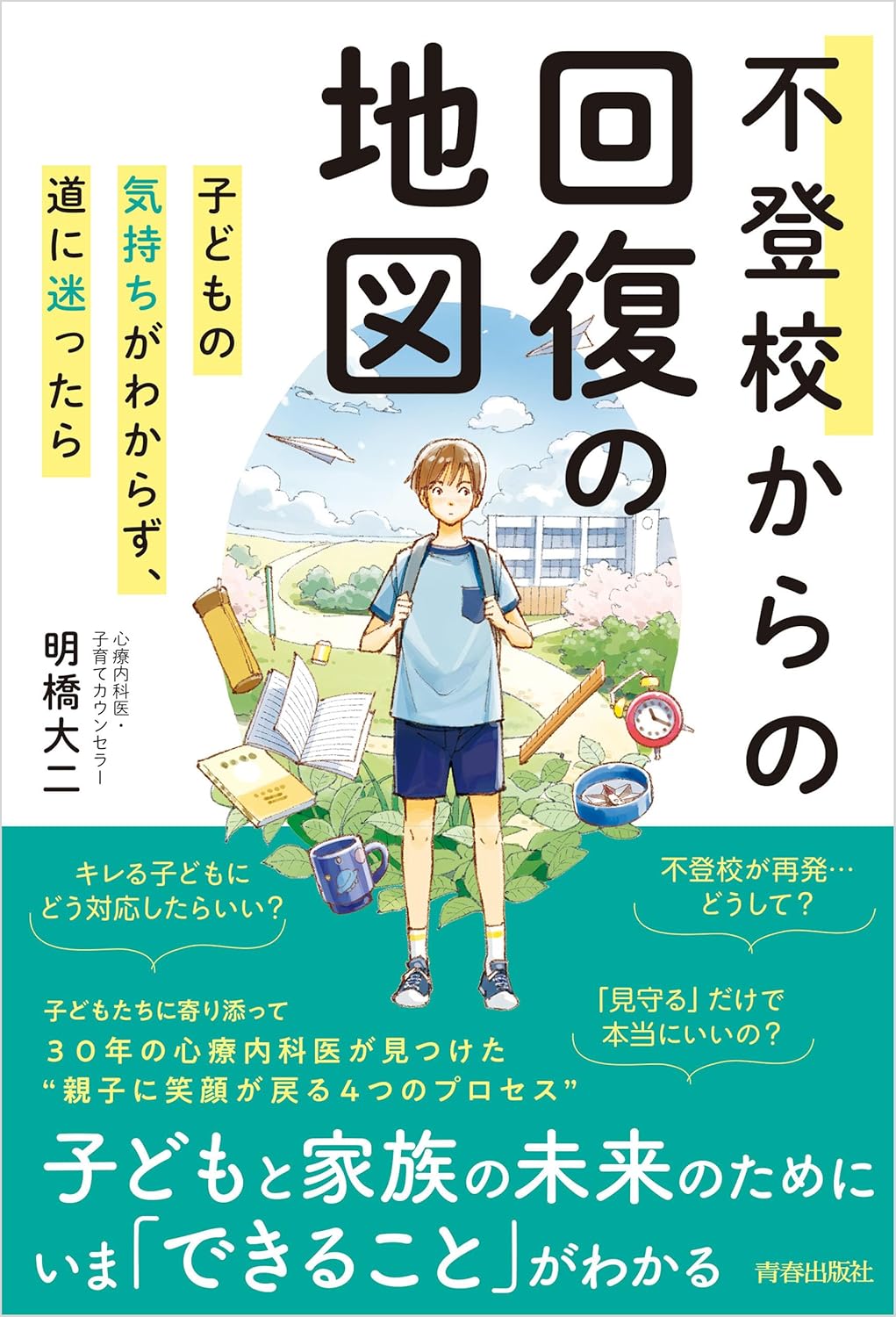キレる、暴力、昼夜逆転 不登校児の問題行動、専門家が教える対処法は?
不登校から回復してゆくプロセスの中で、子どもはさまざまな行動を出してきます。中には親も対応に困るような行動も少なくありません。「キレる」「昼夜逆転」「ゲームばかりやっている」…などの行動を子どもがとるとき、親はどのように受け止め対応すればよいのでしょうか?
「子どもの問題行動にはすべて理由があり、子どもの心の叫びや安心を求めるサインであることが多い」と語るのは、心療内科医で子育てカウンセラーの明橋大二先生。明橋先生の解説を、著書より抜粋して紹介します。
※本稿は、明橋大二著『不登校からの回復の地図』(青春出版社)より一部抜粋、編集したものです。
1.キレる
まず1つ目は、「子どもがキレる」ということです。
しかし子どもは、何の理由もなしにキレたりしません。子どもがキレるのは、多くの場合、「窮鼠(きゅうそ)猫を噛む」という形で出ていることが多いです。要するに、追い詰められたネズミが、必死で反撃して猫を噛むように、子どもは親に追い詰められてその防御としてキレるのです。
親としては、決して追い詰めているのではない、攻撃しているのではない、と思うかもしれませんが、たとえば「もうちょっと早く起きたら?」とか、「ゲームばっかりして」という言葉が、すでに十分、子どもにとっては「責められている」と感ずるのです。
このような、子どもに対する不満、愚痴、文句だけではなく、指示、命令、提案も、場合によっては、子どもを追い詰めることになるので、特に休養期においては、一切そのようなことは言わないことが大切です。
2.親をこきつかう
あれしてくれ、これしてくれ、と親を奴隷のようにこきつかう、という行動が出てくることがあります。親にとってみれば、なんとわがままな、と思うのですが、これは、「学校も行けないような自分は生きている価値がない」と感じている子どもが、そんな自分でも生きていていいのか、ということを確かめようとして起こす行動です。
赤ちゃんのときはどんな親も、子どもが泣いたら対応せざるを得ません。子どもの奴隷みたいな状態だったと思います。それによって赤ちゃんの心には、自分もこの世に存在していいんだ、という気持ちが育つのです。
ちょうどそのように自分の存在を全面肯定してほしい、ということなのです。ですから、そのような要求は、可能な範囲で、受け入れる、ということです。
99%は受け入れて構いません。あと1%の要求とは、たとえば、100万円今すぐよこせ、とか、殺してくれ、とか、どうしても聞けない要求はあります。それは断っていいですが、それ以外はできるだけ受け入れることが必要だということです。
そのように受け入れていると、どんどんエスカレートするのではないかと親は不安になると思いますが、逆です。自分の存在が受け入れられていると分かると、次第に自分から、要求を自制するようになってきます。
3.家庭内暴力
「キレる」行動がさらにエスカレートして、「家庭内暴力」に発展する場合も、多くはありませんがあります。多くは、いじめなど深いトラウマがあって、それを思い出すと、怒りをコントロールできなくなって、家族に当たるなどです。
そのような場合は、「物」に対する暴力や八つ当たりの場合は、基本的にはやらせておく。どうしても壊してもらうと困るものは、あらかじめ避難させておく。
しかし、人間(親)への暴力については、これは「甘んじて受ける」という対応は誤りです。これは、許容しているとどんどん子どもの感覚も麻痺してエスカレートしてゆきますから、「逃げる」という形で拒否することが必要です。
これが続くようなら、専門家への相談が必要なので、躊躇なく専門家に相談してください。しかし多くの子どもは、親が責めたりしなければ、それほど激しい家庭内暴力に至ることはありません。
4.赤ちゃん返り
逆に、赤ちゃん返り、という形でべたべた甘えてくることがあります。これも、赤ちゃんのように甘えることで、「学校にも行けないような自分が、生きていていいのか」という不安を解消するためにやっていることです。
ですから基本的には受け入れて構いません。むしろ、暴力という形でなく、素直に「甘える」という形で出せるのはいいことです。受け入れているうちに、子どもが元気になれば、離れていきます。
5.昼夜逆転
「昼夜逆転」という現象があります。朝まで起きてゲームをやっていて、皆が起きる頃に寝て、昼まで寝ている。こういう様子を見ると、「学校に行かなくてもいいから、せめて朝は皆と同じように起きなさい」というように言いがちです。学校の先生もそのようにアドバイスされることが多いです。しかしこれは誤ったアドバイスです。
「昼夜逆転」は、不登校の原因ではなく、結果です。昼夜逆転しているから、朝起きられないから学校に行けないのではなく、学校に行けないから、昼夜逆転になるのです。
なぜなら、学校に行けない子どもにとって、一番つらいのは、午前中の時間です。皆は学校に行っている。でも自分は行けない。そう思うとつらくなって死にたくなるので、睡眠に逃げるのです。
逆に、不登校の子どもが一番ほっとできる時間が、夜中です。みんな寝静まって、活動していない。責められることもない。ですから、安心してゲームができるのです。自分をずっと責め続けている子どもにとって、昼夜逆転することは、少しでも安心して日々を送るために必要なことなのです。
ですから子どもが元気になってくると、逆に、朝はちゃんと起きるようになりますし、夜も寝るようになります。
ですから私は、親御さんには、一日のどこかでしっかり寝ていればそれでいい、とアドバイスしています。無理やり朝起こさなくてもいいということです。
6.ゲーム
あと多くの親が悩むのが、「ゲームばかりやっている」というものです。しかしこれも、不登校の原因でなく、結果です。ゲーム依存になったから、学校に行けないのではなく、学校がつらくて行けなくなった子どもが、唯一気晴らしできるのがゲームなのです。
学校に行けなくなると、多くの子どもは、ただ授業に出られなくなるだけでなく、友達も失います。外にも出られなくなります。家でじっとしていても、ネガティブなことばかり考えてどんどん落ち込んで、最後には死にたくなります。
そこで少しでも気分転換したいと思って、ゲームをするのです。不登校の子の多くが語るのは、「ゲームの中だけが自分の居場所だった」「ゲームをしているときだけ、唯一生きている気がした」という言葉です。
ですから、無理やりゲームを取り上げようとすると、子どもは血相を変えて怒ります。それだけ、ゲームの世界が命と同じくらい大切なものになっているのです。
そのままゲーム依存になって、廃人になるのではないかと心配する人がありますが、多くの子どもは、元気になるにつれて、学校など外の世界に出かけるようになります。
学校に行くようになれば、自然とゲームをする時間も限られます。決して皆がゲーム依存症になるわけではないのです。ですから私は、ゲームについても睡眠時間さえ確保していればOKと言っています。
昼夜逆転にしてもゲームにしても、親がある程度ルールを決めて、子どもに守らせたいと思う気持ちは分かります。
しかしそれをあまり厳しくすると、結局子どもは守れませんから、叱ることになります。そうすると親子関係は悪化し、家の環境が、安心・安全な場所でなくなります。そちらのほうが、よほど回復にはマイナスだ、ということなのです。
心療内科医・子育てカウンセラー明橋大二著『不登校からの回復の地図』(青春出版社)
不登校児童が増える今、「最近、子どもが学校に行きたがらなくて…」「朝、子どもを起こそうとしても、ちっとも布団から出てこないんです」「このまま、ひきこもってしまうのではと不安です」などの相談を30年以上受けてきた心療内科医が、「これだけは伝えたい」と思ったことをまとめた一冊。